コンペで差をつける"説得力"の源泉 「顧客企業以上に顧客企業のユーザーを知る」セプテーニのユニーリサーチ活用法

株式会社セプテーニは、デジタル広告の企画・設計、運用および効果測定におけるノウハウは業界随一であり、また、生成AIの活用やCRMサービスの提供、そして電通グループとのシナジーのもと、オンライン・オフラインを横断したマーケティングサービスの提供にも力を入れることで、顧客企業のDXを総合的に支援しています。
コンペに向けたリサーチや、デザインシンキングを取り入れたワークショップなど、同社の提案活動の中心には常に“ユーザーの声”があります。その声を迅速かつ確実に取り入れる基盤として、ユニーリサーチが活用されています。
今回は、株式会社セプテーニより、デザイン領域統括 高木 皓平さんと、Septeni Insight Lab. (セプテーニ インサイトラボ)※ 田原 晴加さんに、ユニーリサーチの活用方法や導入効果について詳しく伺いました。
※セプテーニで2021年に発足した、調査の企画から施策への落とし込みを一気通貫で行う専門組織
※本記事の内容は取材日2025年9月10日時点のものとなっています
上流戦略からクリエイティブまで、デザインシンキングとリサーチで顧客企業を支援
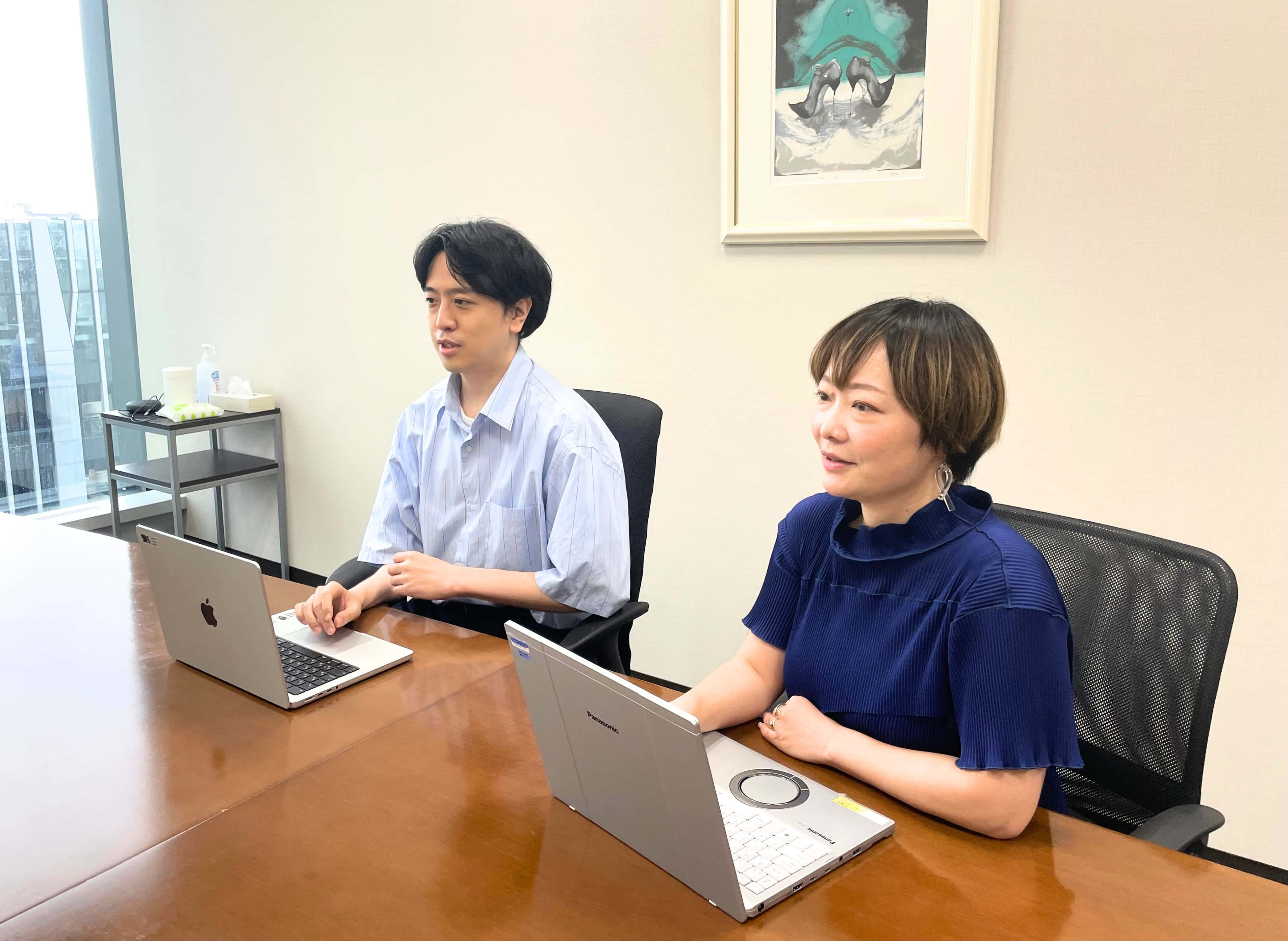 高木 皓平さん(左)と田原 晴加さん(右)
高木 皓平さん(左)と田原 晴加さん(右)
― お二人が担当されている部門の役割について教えてください。
高木さん: 私はパフォーマンスクリエイティブ領域とデザイン領域の2部門を管轄しています。
パフォーマンスクリエイティブ領域はクリエイティブディレクターが所属する組織で、私自身は統括補佐として、制作したクリエイティブのクオリティ管理などを担当しています。
デザイン領域はメンバー全員がデザイナーで構成された部署です。企業の経営戦略やコミュニケーション戦略といった上流の意思決定を、デザインシンキングを用いて支援しています。ワークショップ等の手法を活用して顧客企業と共創的に取り組み、ユニーリサーチ等で得られたユーザー課題を踏まえて方向性を導き出しています。
セプテーニにご相談いただくのは、ブランド定義をより明確にしたい時、新たなターゲットを開拓したい時、あるいは様々な施策をやりきって次の方向性に迷われた時が多いです。我々が戦略の上流からサポートし、最終的にはデザイナーとしてサイトに落とし込んだり、ロゴやネーミングなど具体的な提案までも行います。
田原さん: 私が責任者を務める「Septeni Insight Lab.(セプテーニ インサイトラボ)」は、リサーチの調査設計に専門を持つリサーチ組織と、リサーチ結果を分析し施策につなげることを得意とするコミュニケーションプランニングの組織が一体化した部門です。
リサーチ組織では、コンペに向けた戦略立案のための市場調査、クリエイティブ制作に必要なインサイト把握などを担っています。またコミュニケーションプランニング組織では、顧客企業が課題に直面した際、調査を起点とした解決策をご提案し、その後の施策へとつなげていきます。
ユーザーの声が議論を深め、コンペで差をつけ、受注の後押しになる
― ユーザーインタビューやリサーチを重視している理由を教えてください。
高木さん: ご支援の中でも特に重視しているのがワークショップです。1回2時間、多い時はそれを8回ほど行うこともあり、しっかり時間をかけて取り組んでいます。
ワークショップでは、まず仮説を発散させます。たとえば「自分たちを動物にたとえると?」といった少しユニークな問いを投げかけながら、さまざまな視点で自社サービスを見つめ直していただきます。そこから立てた仮説をもとにユーザーインタビューを実施し、得られた声をフィードバック。さらに議論を重ね、最終的にどんなアイデアや見せ方が最適かを検討し、再びユーザーの反応を取り入れて方向性を定めていきます。
このプロセスにおいて、ユーザーインタビューは欠かせません。ユーザーの声は驚くほど大きな力を持っています。サービスの強みや課題を整理するだけでなく、「ユーザーがこう言っている」という事実が顧客企業のご担当者様にとって会話のモチベーションを高め、議論を盛り上げる重要な材料になります。
また、私たち自身にとっても顧客企業のサービスを深く理解するための貴重な機会でもあります。
田原さん: 一言でいえば、リサーチがあるのとないのでは「顧客企業に対する説得力の重みがまったく違う」と感じています。
コンペの結果を見ても、各社が『素晴らしい戦略を提示する』だけでは差がつかないことが多い。最後の一押しとなるのは、顧客企業のご担当者様が戦略に対して納得感を得られるか、社内で説明できる根拠になるかどうか、といった説得力です。定量的な結果に加え、インタビューで得られるユーザー自身のコメントなど“手触り感のある情報”があることが、プレゼンの印象を大きく左右します。
エンドユーザーを理解し、解像度高く提案できることは、受注にも結びつきやすくなると思います。
よく社内でも話しているのが、「解像度高く提案するためには、顧客企業のことをよく知ることが必要だが、顧客企業以上に知ることは難しい。だからこそ、顧客企業のご担当者様に共感いただいたり、顧客企業の社内を動かしたりするためにより重要なのは、ご担当者様以上にエンドユーザーを知る努力をすることだ」ということ。ですので、時間が許す限り、定量・定性の両面でファクトを提示することが、結果的に信頼度を高めると考えています。
コンペに間に合うスピードと費用感 「カジュアルに生の声を聞ける」ユニーリサーチを導入
― ユニーリサーチを導入されたきっかけについて教えてください。
田原さん: 2021年のSepteni Insight Lab.発足を契機に、調査手法を広げ、定性調査の実績を積み重ねていこうという方針になりました。ちょうど社内でインタビュー調査のニーズも高まっていたこともあり、ユニーリサーチを導入しました。
それまでも調査会社への依頼やチャット形式のツールを使って定性調査に取り組んでいましたが、調査会社は費用が高く、対象者の選定にも時間がかかるため、長くても1ヶ月程度しかないコンペのスケジュールには合いませんでした。また、チャットツールも便利なのですが、より深いインサイトを得るためには直接インタビューすることの重要さも感じていました。
もっとカジュアルにユーザーの生の声を聞ける環境が必要だと感じていたので、期待感を持ってユニーリサーチを使い始めました。
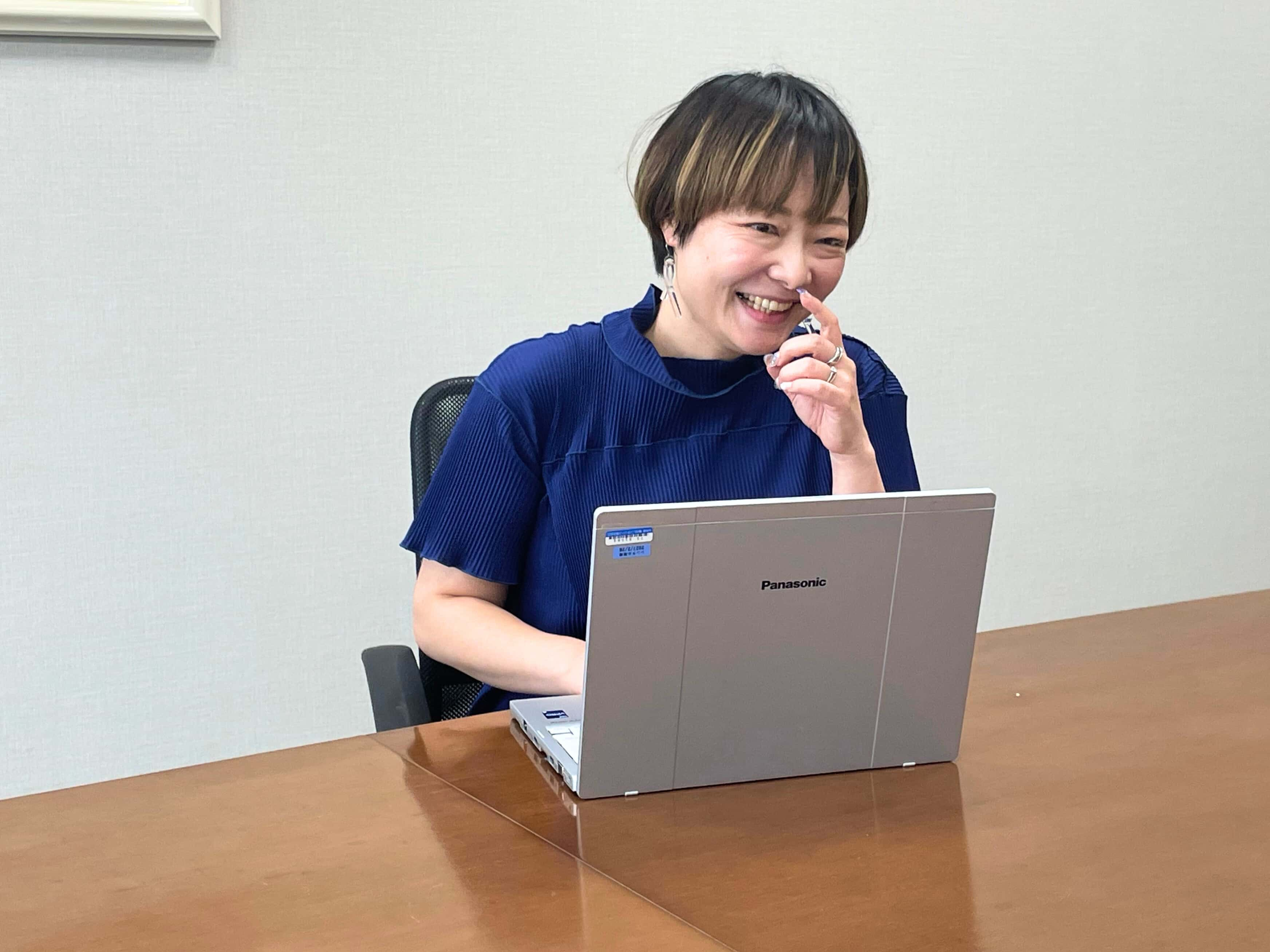
― ありがとうございます。調査会社とは、どのように使い分けていますか?
田原さん: コンペなど費用やスピードに制約がある場合はユニーリサーチを活用しています。一方で、プロのモデレータにお願いしたい場合や、対象者条件が非常に特殊な場合、顧客企業からの依頼でレポート納品がある場合や定量調査と組み合わせて定性調査を実施したい場合などは調査会社に依頼することもあります。
高木さん: 私は、基本的にすべてのリサーチでユニーリサーチを活用しています。アプリを実際に触ってもらいながらUI/UXを確かめたり、HUT(Home Use Test)を行ったりできるので、今はツールを使い分けることなく対応できています。
定性調査で数値インパクトを実現 CVR1.2倍に改善とコンペ受注にも貢献
― ユニーリサーチの導入効果について教えてください。
高木さん: ある企業のサイトでは、メイン訴求が10年近く変わらずに使われていました。改善のためにワークショップとインタビューリサーチを実施。ユーザーの声をもとに「もっとこういう使い方があるのでは?」と顧客企業のご担当者様と一緒に考えながら、言葉やデザインに落とし込んでいった結果、CVRを1.2倍に改善することができました。
ABテストやGoogleアナリティクスを用いた定量的な分析も行っていましたが、実際にユーザーがサイト画面を操作する様子を目の当たりにできたことで、“生の実感”を得られたことが大きな改善につながったと思います。定性調査は「成果が出にくい」と言われがちですが、数字でインパクトを示せた好事例になったと感じています。

田原さん: とある企業では、大きな予算をかけて定期的に定量調査を行っていたのですが、定性調査は実施されていませんでした。そこで、「弊社に調査をお任せいただければ、ご活用されているご予算の中で定性調査も組み合わせ、新しい価値を出せます」と提案しました。
調査会社に依頼すると数百万円規模になりますが、ユニーリサーチであれば費用を抑えて実施できます。定量的な事実だけでなく、エンドユーザーの生の声を知ることができるという“プラスアルファの価値”がご発注の後押しとなりました。納品したレポートの評価も高く、成果につながっています。
質と量を兼ね揃えたパネル チャット調査では得られない深掘りの価値
― ユニーリサーチの気に入っているポイントを教えてください。
高木さん: まずはツールの「見やすさ」ですね。画面がシンプルなので、専門知識不要で誰でもインタビューを実施できます。実施に困ることはありません。
費用についても、当社の営業担当者から「ユーザーインタビューっていくらかかるの?」と聞かれて金額を答えると、思った以上に手頃だと驚かれることが多いです。
パネルも充実していますよね。ニッチなテーマでもすぐに対象者を見つけることができるので、幅広く集められます。そして、回答の質がとても高い。真摯に答えてくださる方が多く、いつも感謝しています。
インタビューと聞くと「厳しい意見が出てしまうのでは」と不安に感じられる方もいます。ご批判を受け止めることも重要ですが、実際に100人近くの方にお話を伺ってわかったのは、ポジティブな発見の方が多いということです。自分たちでは気づけなかった可能性をインタビューから導き出せることがあり、大きな価値を感じています。
田原さん: 「見やすさ」は私も気に入っている点ですが、特にありがたいのはスピード感です。応募いただいた方のリストを確認しながら、その場で「この人に聞こう」と選んで速やかに実施できるのは非常に使いやすいですね。ユニーリサーチでは募集と並行してインタビューを進められるため、スピード感があって助かっています。
チャット型のインタビューも使うのですが、どうしても決まった質問に沿って進行しがちです。しかし、定性調査の目的は「なんで?」を深掘りすること。ユニーリサーチなら、その場で得られた情報に対してさらに質問を重ねられるので、より本質に迫ることができます。
生成AI時代に問われる、広告代理店の新しい挑戦とは
― 今後の展望について教えてください。
高木さん: 生成AI時代において、広告代理店はどうあるべきかが議論されています。私自身は、そんな時代だからこそデザインシンキングが重要で、それによって企業の背中を押すことが代理店の価値になるはずだと考えています。質の高い意思決定サポートができるチームを目指し、ケイパビリティを高め、実績を積み重ねていきたいと考えています。
田原さん: 今後、生成AIによってクリエイティブ制作や広告運用そのものが高いレベルで自動化されるようになると、私たちのようなエージェンシーの介在価値が出しづらくなるという予想もあります。そうなった場合、顧客企業の事業成長に貢献するために我々がより注力すべきなのは売れるプロダクトづくりだと思います。ユーザーの声をキャッチし、プロダクト開発にフィードバックしていく。その重要性は今後さらに高まっていくはずですので、そこを担えるチームになっていきたいですね。








