
ホームユーステスト(HUT)とは?メリット・デメリットやモニター謝礼の相場を解説
ユーザーが自宅で商品をお試しする「ホームユーステスト」。商品に関する評価や意見、感想を得るための調査として一般的な調査方法です。 ホームユーステストのメリット・デメリットやモニター謝礼・費用の相場などを解説します。
- ホームユーステスト(HUT)とは? 目的や会場調査との違い
- ホームユーステスト(HUT)の目的
- ホームユーステスト(HUT)と会場調査(CLT)との違い
- ホームユーステスト(HUT)の提示方法・評価方法
- ホームユーステスト(HUT)の提示方法
- ホームユーステスト(HUT)の評価方法
- ホームユーステスト(HUT)のメリット
- 日常的な環境で試用できる
- 一定期間経過後の評価を調査できる
- 対象ユーザーのファン化につながる
- 全国のユーザーを対象に調査可能
- ホームユーステスト(HUT)のデメリットと対策
- ユーザーが途中離脱する可能性がある
- 情報漏洩リスクがある
- テスト環境に一貫性がない
- 実際の反応を見ることができない
- 謝礼だけでなく、発送・返送費用がかかる
- ホームユーステスト(HUT)実施の流れ
- ホームユーステスト(HUT)の費用や謝礼の相場
- ユニーリサーチでホームユーステストの実施が可能
- ホームユーステスト(HUT)の導入事例
- 国内最大級のダイレクトリサーチサービス『ユニーリサーチ』
ホームユーステスト(HUT)とは? 目的や会場調査との違い
ホームユーステスト(HUT:Home Use Test)とは、対象ユーザーの自宅で一定期間製品を試用(試飲、試食)してもらい、評価や意見を得る調査方法です。食品、飲料、化粧品、日用品などの調査としてよく利用されますが、中には文具や調理器具、電化製品などのホームユーステストも実施されています。 自宅で試用してもらうため、個々のユーザーが日常的な環境で利用した場合の評価を得ることができます。また、数日~数か月間といった単位で試用してもらうこともできるので、効果を実感するまでに期間を要する商品にも向いている調査です。 「商品モニター」という言葉もホームユーステストと同義で使用されることがありますが、比較的短期間で終了し、簡単なアンケートや口コミ形式で意見を集める調査を指すことが多いようです。
ホームユーステスト(HUT)の目的
ホームユーステストを行う主な目的は以下の通りです。
新商品: 発売前の商品の評価チェック、新商品に複数の候補がある場合の絞り込み
既存商品: 改善点の洗い出し、リニューアル案が複数ある場合の絞り込み
競合商品: 競合商品の強みの分析、同条件で調査し自社商品と比較
ホームユーステスト(HUT)と会場調査(CLT)との違い
会場調査(CLT:Central Location Test)とは、対象ユーザーの自宅ではなく、特設会場や自社などの指定の場所で、商品を試用(試飲、試食)してもらい、評価や意見を得る調査方法です。 ホームユーステストと比べると情報の秘匿性が高く、すべての対象ユーザーに対して同一条件で調査を実施できることがメリットですが、普段の生活に即した使用や一定期間使用した場合に関する評価を得ることはできません。
▼「会場調査」についてより詳しい記事はこちら

ホームユーステスト(HUT)の提示方法・評価方法
ホームユーステストの提示方法と評価方法は以下の通りです。
ホームユーステスト(HUT)の提示方法
ホームユーステスト(HUT)におけるテスト製品の提示方法には以下の3種類があります。
ブランデッドテスト(Branded Test) | 「ブランデッドテスト」は、ブランド名やメーカー名、実際のパッケージなどをユーザーに明らかにした上で試用してもらうテストです。例えば、スーパーの店頭に並ぶそのままのパッケージの缶ジュースを手に取って試飲し、評価してもらいます。 実際の購買状況に近い条件なので市場での売れ行きを推測しやすく、パッケージ変更の場合の効果も測定できるのがメリットです。 一方で、ブランドやメーカーの評価が高い場合、それだけで高得点になりやすく、中身を改良しても評価の差が出づらいこともあります。 |
ブラインドテスト(Blind Test) | 「ブラインドテスト」は、ブランド名やメーカー名、パッケージをユーザーに開示せずに試用してもらうテストです。例えば缶ジュースなら、無地のパッケージを用意し、その状態で試飲してもらいます。 ブランド力に左右されず、純粋に商品自体の評価を測定できること、小さな違いも評価の数字に表れやすいことがメリットです。 一方で、実際の購買状況ではブランドやパッケージが少なからず影響するため、売れ行きを予測するのは難しくなります。また、パッケージを隠すリパック作業などの追加コストがかかります。 |
ブランデッドテストとブラインドテストの組み合わせ | ブランデッドテスト、ブラインドテストにはそれぞれメリット・デメリットがあるため、提示方法を組み合わせるという手法もあります。 例えば、同じグループにブラインドテスト→ブランデッドテストを順に行ったり、2つのグループそれぞれに片方ずつテストを行ったりすることで、その評価の差からブランド力の影響を見ることができます。 |
ホームユーステスト(HUT)の評価方法
ホームユーステスト(HUT)の主な評価方法は以下の4つです。
モナディックテスト(Monadic Test) | 「モナディックテスト」では、単一の製品を試用し、絶対評価を行います。他の商品と比較したことによる評価への影響がなく、実際の購買時に近い状況での評価を行うことができます。 実際の調査時には比較のため、「製品Aを評価するグループ」「製品Bを評価するグループ」と製品ごとに母集団を分けることが多いでしょう。その分、テストする製品の数に応じて調査費用がかさむ点はデメリットと言えます。 |
直接比較法(Direct Comparison Test) | 「直接比較法」では、複数の製品を同時に試用し、比較評価します。短時間で順位付けができ、評価項目の感覚差が出やすい製品の調査に特に有効です。 一方で、順番が結果に影響を及ぼす順序効果や、違いを誇張して捉えるコントラス効果の影響が出やすいのがデメリットです。それらのバイアスを取り除くためには、最初にウォームアップ用のテスト製品を評価したり、調査グループごとに順番を入れ替えたりといった対策があります。 直接比較法の中にさらに、以下の2つの手法があります。 |
シークエンシャルモナディック法(Sequential Monadic Test) | 「シークエンシャルモナディック法」では、複数の製品を試用して絶対評価を行い、すべての製品の絶対評価が終わった後、全製品を比較、評価します。 各製品の絶対評価と相対的な評価の両方を一度に比較でき、母集団を分ける必要もないのがメリットです。 ただし、連続使用により評価がブレやすいのは課題です。味を評価するのであれば1つの製品の評価を終えるごとに口直しの水を摂ってもらう、香りを評価するのであれば換気を徹底してもらうなどの工夫が必要です。 |
プロトモナディック法(Proto-Monadic Test) | 「プロトモナディック法」では、1つの製品を試用して絶対評価を行い、残りのすべての製品は試用後、最初の商品と比較評価します。競合商品を上回れるか、改良品が現行品に勝てるか、といったことを短時間で見極めることに適しています。 回答者は評価基準が明確な状態で比較しやすい一方で、最初の1つの製品の印象が強く残る順序効果の影響も大きいため、母集団をいくつかに分けて最初の製品を入れ替えるなどの工夫が重要です。 |
ホームユーステスト(HUT)のメリット
ホームユーステストの主なメリットは以下の4つです。
日常的な環境で試用できる
ユーザーの自宅で商品を試用できるため、日常的な環境で使用した場合の評価や意見を得ることができます。 また、ユーザーの家族の反応も同時に収集できる、商品ターゲットのリアルな生活環境がわかる、といった副次的な効果も見込めます。
一定期間経過後の評価を調査できる
一時的な使用だけでなく、一定期間継続して使用した後やその途中経過での評価も調査することが可能です。 数日~数か月後の継続利用後の評価、感想を取得する調査もあれば、日ごと、週ごとに日記のように記録してもらう調査もあります。
対象ユーザーのファン化につながる
ホームユーステストを通して実際の商品を一定期間利用することで、使い心地を実感したユーザーが新たなファンになってくれることがあります。
全国のユーザーを対象に調査可能
会場調査のように特定の場所に集まる必要がないため、都市部以外の全国各地ユーザーを対象に調査することができます。広い規模で展開している商品の試用テストをする場合はホームユーステストが向いています。
ホームユーステスト(HUT)のデメリットと対策
ホームユーステストの主なデメリットは以下の3つです。デメリットを軽減するための対策も一緒にご紹介します。
ユーザーが途中離脱する可能性がある
ホームユーステストでは一定期間の試用が必要なことが多く、その間の工程も多い ため、ユーザーと連絡が取れなくなる、途中経過に関して指示通りに記録されていない、などの途中離脱が発生する可能性が単発の調査よりも高いです。 対策としては、途中離脱者が出ることを見込んだ十分なサンプル数を確保すること、テストの手順をシンプルにすることなどが挙げられます。
情報漏洩リスクがある
テスト用の商品をユーザーに渡すため、商品情報や調査内容の漏洩リスクがあります。ユーザーやその家族が善意でSNSにクチコミを上げてしまい、発売前の商品情報が漏洩してしまう可能性もあります。 情報漏洩リスクを下げるためには、ホームユーステストの依頼前後で、受け取った商品や情報の取り扱い方をしっかり伝えることや、そもそもブランド名を明かさないブラインドテストにすることなどが重要です。
テスト環境に一貫性がない
ユーザーごとに自宅の環境は異なるため、商品の本来の効果を発揮できない場合があります。会場調査と違って試用環境を直接制御することができないため、ユーザーが本来の指示と異なる方法で試用することも考えられます。 テスト環境を可能な限り統一するために、テスト環境や使用方法の指示を書いた説明書はシンプルかつどのユーザーにもわかりやすいように作成することが必要です。
実際の反応を見ることができない
ホームユーステストでは、ユーザーが実際に製品を試用している様子を見て、そこから隠れたニーズや評価を汲み取ることはできません。ユーザーからのフィードバックにアンケートだけでなくインタビューも取り入れて実際の声色や表情を観察するといった工夫も大切です。実際に試用する様子を見る必要がある場合は、会場調査や訪問調査を利用しましょう。
▼「訪問調査」についてのより詳しい記事はこちら
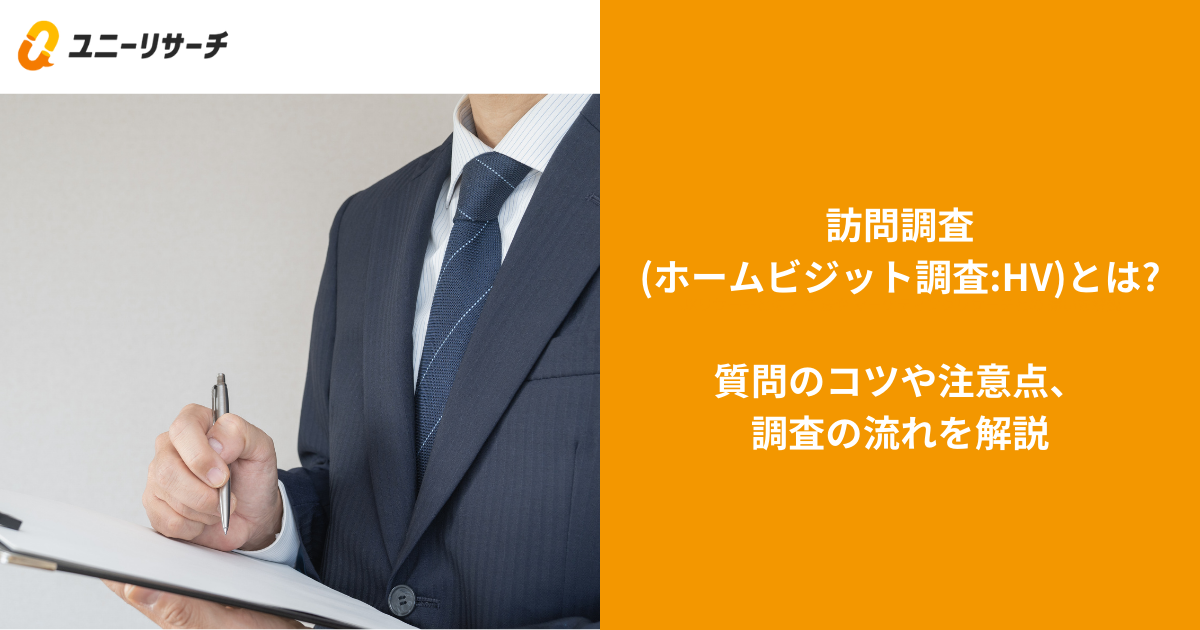
謝礼だけでなく、発送・返送費用がかかる
ホームユーステストでは、製品自体のコストや対象ユーザーに支払う謝礼だけでなく、試用する製品をユーザーの手元に届け、調査内容によっては送り返してもらうための発送・返送費用がかかります。また、調査に必要な資料や緩衝材を入れるとサイズが大きくなったり、製品や季節によっては冷蔵・冷凍便の利用が必要だったりすることで、当初の予想以上に費用が膨らむこともあります。 あとから追加コストが発生しないよう、事前に調査フローをシミュレーションして正確な費用を把握すること、得られる結果と費用のバランスを考えた調査設計をすることが重要です。
ホームユーステスト(HUT)実施の流れ
ホームユーステスト実施の大まかな流れは以下の通りです。
調査企画: 調査の目的や試用環境、商品提示方法、評価方法などを決定
スクリーナーの作成: 目的にあったユーザーを選定するための事前調査票(スクリーナー)の作成
▼「スクリーナーの作り方」についてより詳しい記事はこちら

モニターの募集、選定: 調査会社やセルフ型リサーチサービス、自社パネルなどを利用して調査モニターを募集、スクリーナーで調査参加ユーザーを選定
テスト商品の発送: 選定されたユーザーの自宅に試用してもらう商品を発送
調査実施: ユーザーが受け取った商品を試用
評価の回収、謝礼の支払い: インタビューやアンケートでユーザーによる評価を回収、ユーザーへの謝礼の支払い(調査条件によっては、テスト商品の回収)
▼「インタビュー」についてのより詳しい記事はこちら


▼「アンケート」についてのより詳しい記事はこちら
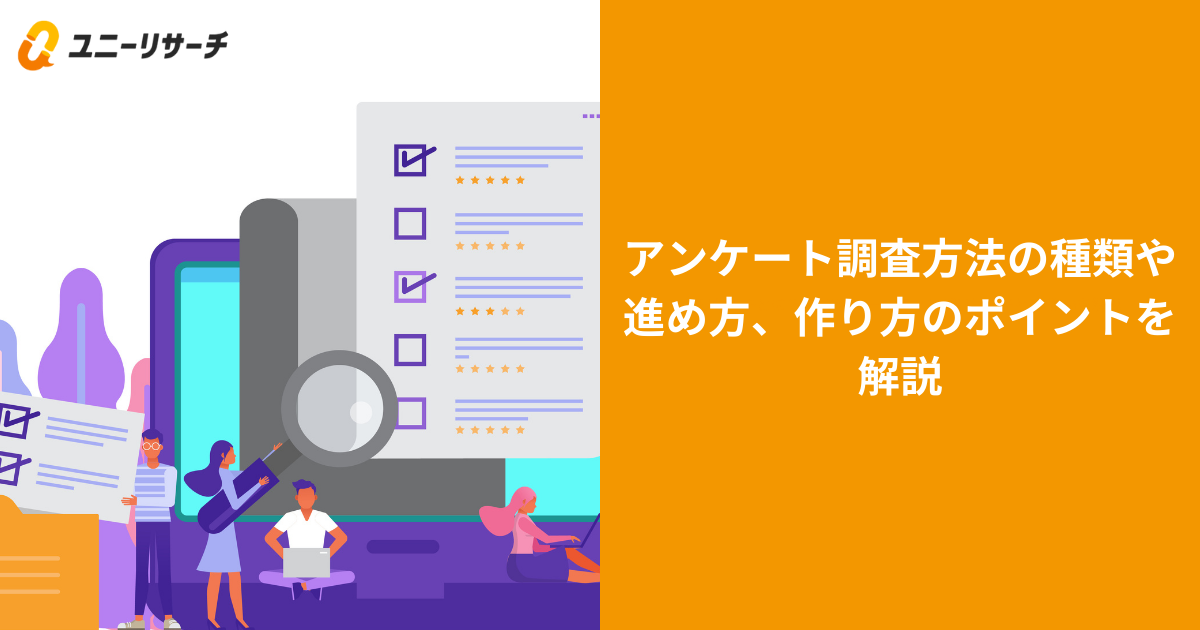

集計、分析: 集めた評価を集計、分析し、調査レポートを作成
ホームユーステスト(HUT)の費用や謝礼の相場
ホームユーステストの謝礼金額は幅広く、調査の期間や方法、対象ユーザーの要件などによって異なります。一般的には1,000~5,000円程度のことが多いでしょう。簡単な調査であれば商品の提供と500円程度の謝礼の場合もありますし、長期にわたる調査であれば万単位の謝礼になることもあります。
参考例として、ユニーリサーチでのホームユーステスト時の謝金相場をご紹介します。
依頼内容 | モニター期間 | フィードバック(例) | 謝礼金額 |
|---|---|---|---|
食品のサンプルテスト | 2週間 | アンケート2回 インタビュー1回 | 3,000円〜5,000円 |
英語学習アプリのテスト | 1ヶ月 | アンケート2回 | 3,000円〜5,000円 |
ウェアラブル端末のテスト | 1ヶ月 | アンケート4回 インタビュー1回 | 10,000円〜15,000円 |
新型炊飯器のテスト | 1ヶ月 | アンケート2回 インタビュー1回 | 10,000円前後 |
3種類の洗濯用洗剤のテスト | 2週間 | アンケート3回 | 3,000円〜5,000円 |
ホームユーステストを調査会社に外注する場合、依頼範囲や対象ユーザー数によって金額が異なるため見積もりをとる必要がありますが、数十万~数百万円程度と幅があるようです。 自社ですべて行う場合にかかる費用は、テスト商品の原価、商品の発送・返送費用、ユーザーへの謝礼ですが、その分社内での大きな労力が必要なこと、新規顧客に対する調査の場合はモニターを集めにくいことなどが難点です。
ユニーリサーチでホームユーステストの実施が可能
株式会社プロダクトフォースが運営するダイレクトリサーチサービス 「ユニーリサーチ」では、募集開始まで最短5分というスピードでホームユーステストの対象となるユーザーを全国から募集することができ、モニター募集、選定、テスト内容の教示から、実際のサンプル商品の利用、アンケートやインタビューでのフィードバックの回収までをセルフ型で手軽に行なっていただくことが可能です。また、有料オプションの「ユニーリサーチ便」でホームユーステスト時の商品配送および回収を依頼いただくこともできます。
初期費用、月額費用なし、モニター人数に応じた料金設計で、最長2ヶ月の期間中無制限でアンケートやインタビューによるフィードバックを回収することができます。また、異なる調査にまたがってのリピートオファーも可能ですので、最初にオンラインインタビューのみを行い、その参加者にホームユーステストを依頼する、といった活用方法もございます。
料金体系は次の通りです。
SMALL | モニター人数 ~10名 | 100,000円 | 最小限の小規模検証におすすめ |
BASIC | モニター人数 ~20名 | 180,000円 | サービスローンチ前の最後の検証をしたい企業様向け |
ADVANCED | モニター人数 ~50名 | 300,000円 | 定量データの取得を目的とした大規模調査におすすめ |
※上記金額に加えてモニターへの謝礼金額を3,000円〜の任意の金額で設定できます。
ユニーリサーチのホームユーステストについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。
セルフサービステスト[PoC(概念実証)・ホームユーステスト] | ダイレクトリサーチ(セルフ顧客調査)のユニーリサーチ (uniiリサーチ)
ホームユーステスト(HUT)の導入事例
お客様主語の「ものづくり」を目指す「雪印メグミルク株式会社」様には、ユニーリサーチセルフサービステストの前身サービスである「ユニーリサーチモニター」をご活用いただきました。スピーディーかつ頻繁にお客様の声を聞いて開発を進めたいと考えて、コストを抑えながらもすぐにフィードバックを得られるサービスを探していたところ、ユニーリサーチに出会い、導入されたそうです。
とあるブランド商品のリニューアルに関する検証のためのホームユーステストには250名の応募があり、最終的に19名の方に1週間のサンプル利用後のアンケートとインタビューの調査を実施しました。
実際に活用いただき、ホームユーステストの対象者選定と日程調整の楽さやアンケート設問数やインタビュー回数に制限がないことについてのご好評をいただきました。また、最初はハードルを感じていたセルフインタビューもトライしてみると意外と楽しく、インタビューを通して実際のお客様の声を聞くことによって得るものは大きいと感じられたそうです。
▼「雪印メグミルク株式会社」様のホームユーステスト導入事例について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
商品のリニューアル検証をホームユーステストで実施 雪印メグミルクが目指すお客様主語の「ものづくり」
国内最大級のダイレクトリサーチサービス『ユニーリサーチ』
「ユニーリサーチ」は、調査会社を介さずに「最短当日」でリサーチを開始でき、コストは「従来の10分の1以下」に抑えることが可能な国内最大級のダイレクトリサーチサービスです。数万人規模の多様なユーザーにアクセスでき、基本属性や事前質問によるスクリーニングにより、目的に合わない対象者とのミスマッチを防げます。
スタートアップ企業や大手企業の新規事業部門など、従来の調査サービスを十分に活用できていなかった層を中心に導入が進み、2025年7月時点で登録企業は3,000社、累計リサーチ件数は6万件を突破しました。この機会に、スピーディかつ柔軟なリサーチを実現する「ユニーリサーチ」をぜひご活用ください。












