
アンケート結果の分析方法とまとめ方 自由記述のデータ集計方法も解説
マーケティングリサーチでよく行われる「アンケート調査」の結果を活用するためには、分析が重要です。この記事では、アンケート調査実施後の分析手順や集計・分析方法の種類、分析結果のまとめ方の注意点などについて解説します。
自由記述の回答の集計・分析方法について詳しく触れているので、定性データの扱いに悩んでいる方にも役立つ内容です。ぜひ参考にしてください。
- アンケート調査の基礎知識
- アンケート調査とは?
- アンケート調査のプロセス
- アンケート結果の分析手順
- アンケート結果を集計
- 集計したデータを分析
- 分析結果をまとめる
- アンケート結果の集計方法
- 単純集計
- クロス集計
- 自由記述の集計
- 【基本編】 集計結果の分析方法
- 度数分布分析
- 平均値・中央値分析
- 【応用編】高度な分析方法
- 相関分析
- 単回帰分析
- 重回帰分析
- 決定木分析
- 主成分分析
- 因子分析
- コレスポンデンス分析
- クラスター分析
- 階層クラスター分析
- 非階層クラスター分析
- アソシエーション分析
- 時系列分析
- 自由記述の分析
- 数値の場合
- テキストの場合
- 自由記述アンケートの集計・分析方法について深掘り!
- Excelを活用した手動集計
- アフターコーディングによる分類と定量化
- テキストマイニングによる自動分析
- 外部ツールとの連携による自動化
- アンケート分析を効果的に行うためのポイント
- 分析目的の明確化
- アンケートデータの整理と前処理
- 全体像の把握
- グラフ等を用いた視覚的な分析
- 相関関係を把握する
- 分析結果のまとめ方の注意点
- 適切な種類のグラフを選ぶ
- 棒グラフ
- 円グラフ
- 帯グラフ
- 折れ線グラフ
- 散布図
- デザインやデータの順番を調整する
- アンケートなら国内最大級のダイレクトリサーチサービス『ユニーリサーチ』
アンケート調査の基礎知識
アンケート調査を効果的に活用するためには、その基本的な知識を理解することが重要です。ここでは、アンケート調査の概要とそのプロセスについて簡単にご紹介します。
アンケート調査とは?
「アンケート調査」とは、特定のテーマや課題に関する意見や情報を収集するために、様式化した同一の質問に対して多くの人々の回答を得る調査方法です。マーケティングリサーチや学術研究など、幅広い分野で活用されています。
▼「アンケート」についてのより詳しい記事はこちら

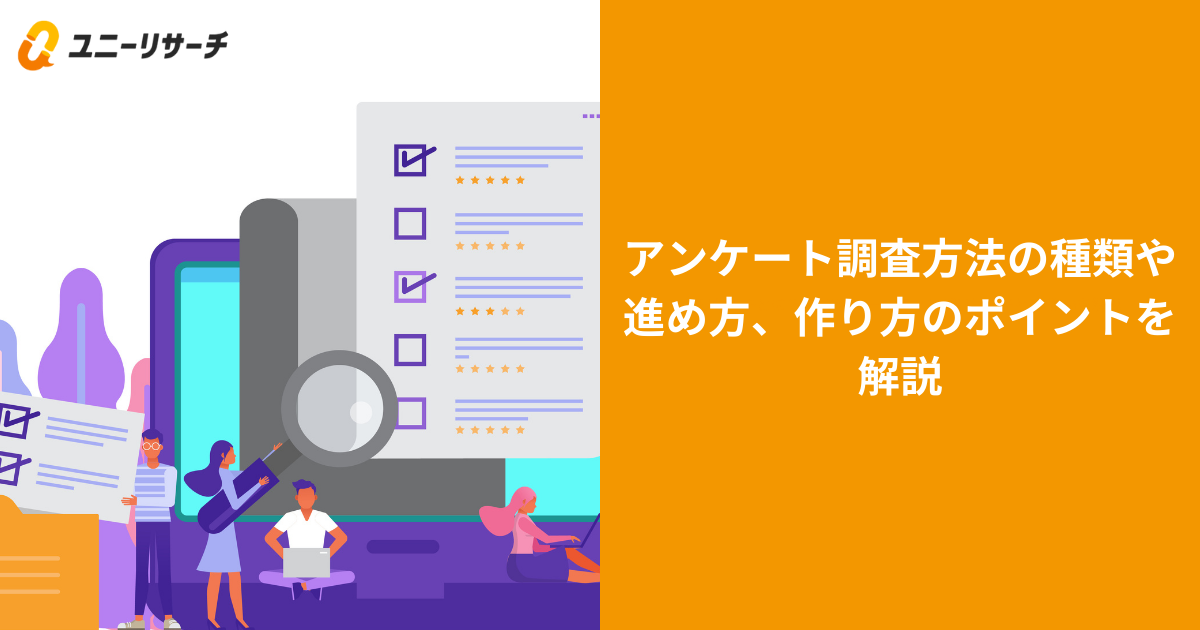
アンケート調査のプロセス
アンケート調査は、以下のようなプロセスで進行します。本記事では、特に「6. データの回収と整理」「7.データの分析」に焦点を当てて解説します。
調査目的の設定
調査設計
アンケート作成
スクリーニング調査の実施
調査の実施
データの回収・集計
データの分析
マーケティング施策への活用
▼「アンケートの作り方」や「回答率の上げ方」についてのより詳しい記事はこちら
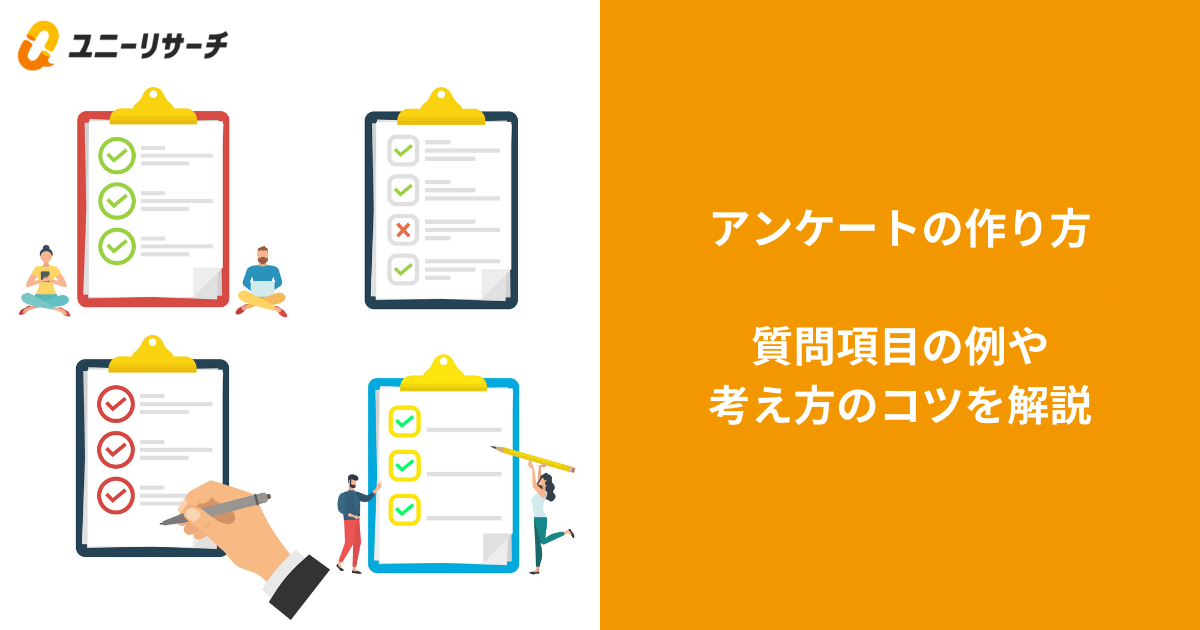
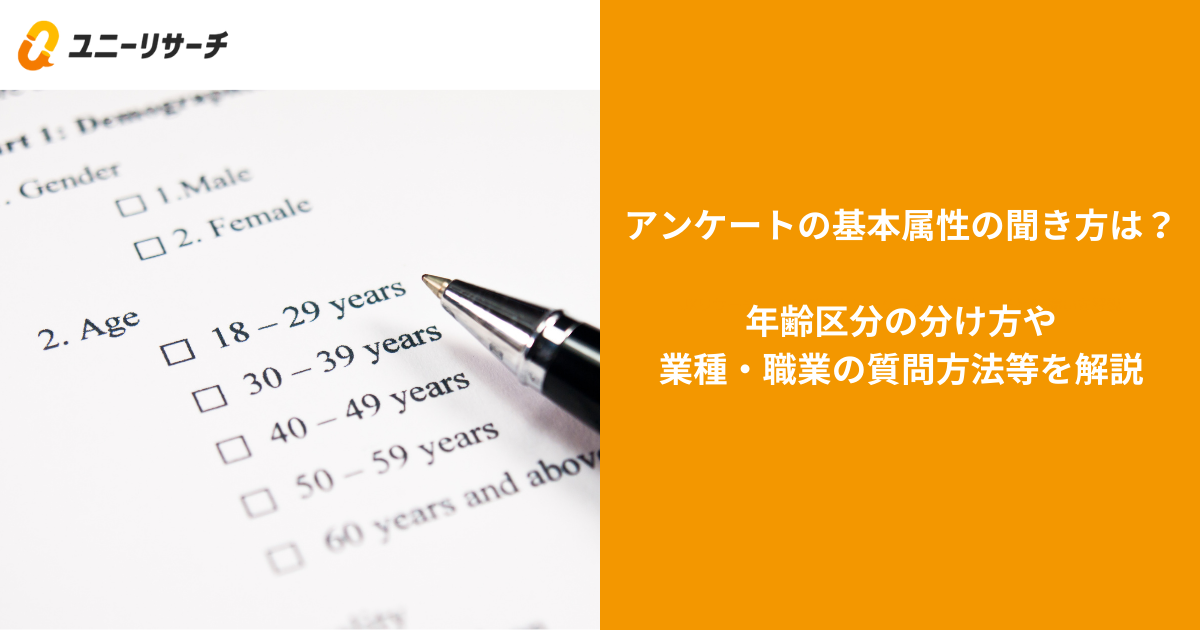
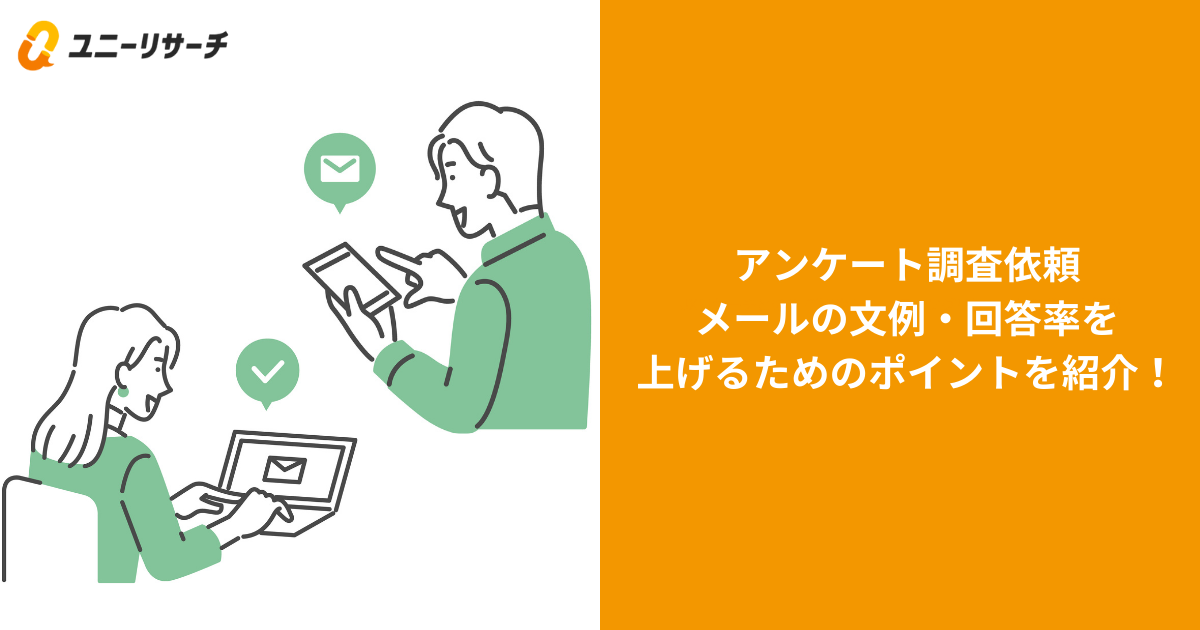

アンケート結果の分析手順
アンケート結果を分析する時の手順について解説します。それぞれの段階の詳しい内容については後の章で解説します。
アンケート結果を集計
アンケートの回答結果を収集し終わったら、データを整理し、集計します。「単純集計」「クロス集計」や自由記述の集計を行い、データの概要を把握できるようにします。
集計したデータを分析
集計したデータを元に、詳細な分析を行います。調査の目的や事前の仮説をもとに、知りたいことやそのヒントがわかるような適切な分析方法を選ぶことが重要です。
分析結果をまとめる
分析した結果を報告書やプレゼンテーションにまとめます。視覚的にわかりやすいようにグラフ等を用いて、関係者にとって理解しやすい内容とし、活用方法についての有効な議論ができるようにします。
アンケート結果の集計方法
アンケート結果の基本的な集計方法について解説します。
単純集計
「単純集計」は、それぞれの質問に対する回答数や割合を算出する基本的な集計方法です。選択肢ごとの回答数や割合、平均値などを求めることで、全体の基本的な傾向を把握することができます。
クロス集計
「クロス集計」は、2つ以上の質問の回答を組み合わせて分析する手法です。単純集計だけでは分からない、もう一段階深堀りした情報を把握することができます。例えば、性別・年齢別の回答傾向を比較することで、特定のグループ(例:30代の女性)に特徴的な結果があるかどうかを明らかにできます。
自由記述の集計
自由記述の場合、回答が「数値」か「テキスト」かで集計方法が異なります。「数値」の場合は平均値、中央値、標準偏差値などを算出します。 「テキスト」の場合は一覧表を作成し、カテゴリごとに分類して傾向や代表的な意見を抽出したり、頻出する特定のキーワードの個数を調べたりします。その際、後述する分析方法の「テキストマイニング」や「アフターコーディング」を、ツールを用いて先に行うことで集計の効率化を図る方法があります。
【基本編】 集計結果の分析方法
アンケート結果集計後の分析方法を紹介します。
分析方法 | 活用シーンの例 |
|---|---|
度数分布分析 | 5段階評価の回答がどの評価に集中しているかを把握したいとき |
平均値・中央値分析 | 価格や満足度などの数値データの中心傾向を知りたいとき |
度数分布分析
「度数分布分析」は、データを一定の範囲(階級)に分け、それぞれの範囲に該当するデータの数(度数)を集計する方法です。例えば、5段階評価のアンケート結果で、各評価の選択数を集計することで、全体の傾向を視覚的に理解できます。この分析により、データの分布や偏りを把握しやすくなります。
平均値・中央値分析
「平均値・中央値分析」は、数値データの中心傾向を把握するための基本的な手法です。平均値はすべての値を合計し、データの個数で割ったもので、全体の傾向を示します。一方、中央値はデータを昇順または降順に並べた際の中央の値であり、外れ値の影響を受けにくい特徴があります。両者を併用することで、より正確な分析が可能です。
【応用編】高度な分析方法
より深い洞察を得るための高度な分析方法を紹介します。
分析方法 | 活用シーンの例 |
|---|---|
相関分析 | 顧客満足度と再購入意向など、2つの変数間の関係性を把握したいとき |
単回帰分析 | 広告費用が売上に与える影響など、1つの要因が結果にどう影響するかを分析したいとき |
重回帰分析 | 価格、品質、サービスなど複数の要因が顧客満足度に与える影響を同時に分析したいとき |
決定木分析 | 顧客の属性や行動から購買傾向を分類し、ターゲット層を特定したいとき |
主成分分析 | 多くの評価項目を少数の要因に要約し、全体の傾向を把握したいとき |
因子分析 | 複数の質問項目の背後にある共通の因子を特定し、データの構造を明らかにしたいとき |
コレスポンデンス分析 | 顧客の属性と購買傾向の関係を視覚的に把握し、マーケティング戦略に活かしたいとき |
クラスター分析 | 顧客を類似性のあるグループに分類し、それぞれの特徴を明らかにしたいとき |
アソシエーション分析 | 「〇〇を購入した人は△△も購入する」など、商品の組み合わせの傾向を把握したいとき |
時系列分析 | 時間の経過によるデータの変動を分析し、季節性やトレンドを把握したいとき |
自由記述の分析 | 自由記述で得られた数値データの傾向を把握したいときや、テキストデータからキーワードや感情の傾向を抽出したいとき |
相関分析
「相関分析」は、2つの変数間の関係性を数値で表す手法です。例えば、顧客満足度と再購入意向の相関を分析することで、両者の関係性を明らかにできます。相関係数は-1から+1の間で表され、1に近いほど正の相関が強く、-1に近いほど負の相関が強いことを示します。
単回帰分析
「単回帰分析」は、1つの独立変数(原因となる要素)が従属変数(結果となる要素)にどのような影響を与えるかを分析する手法です。例えば、「広告費(独立変数)」が「売上(従属変数)」にどのように影響するかを分析する際に用いられます。この分析により、独立変数の変化が従属変数にどのように影響するかを予測できます。
重回帰分析
「重回帰分析」は、複数の独立変数が従属変数に与える影響を同時に分析する手法です。例えば、「価格」「品質」「サービス」といった複数の要因(独立変数)が「顧客満足度(従属変数)」にどのように影響するかを明らかにする際に用いられます。この分析により、各要因が結果に与える影響の大きさや方向性を把握できます。
決定木分析
「決定木分析」は、データの分岐を樹形図で示し、ある結果の原因となっている重要な変数やその関係を明らかにします。樹形図にまとめることで、特定の結果につながる条件を直感的に理解しやすくなります。
主成分分析
「主成分分析」は、多くの変数を少数の主成分に要約することで、データの構造を簡潔に表現する分析方法です。多数のアンケート項目を少数の要因にまとめ、全体の傾向を把握することができます。
例えば、「製品の耐久性」「製品の使用感」「デザインの美しさ」を「製品の品質」、スタッフの「親切さ」「問題解決能力」「ユーザーへの配慮」を「カスタマーサービス」というような要約をします。
因子分析
「因子分析」は、アンケートなどの複数の質問項目(観測変数)から、背後にある共通の要因(因子)を見つけ出すための統計的手法です。
例えば、顧客満足度に関するアンケートで、「スタッフの対応」「商品の品質」「価格の妥当性」など複数の項目がある場合、因子分析を用いることで、これらの項目が「サービスの質」や「コストパフォーマンス」といった潜在的な因子に集約されることがあります。
このように、因子分析を活用することで、観測されたデータの背後にある構造を明らかにし、より効果的な意思決定や戦略立案に役立てられます。
コレスポンデンス分析
コレスポンデンス分析は、クロス集計表のデータを視覚的にわかりやすくするための手法です。この分析では、カテゴリ同士の関係性を散布図として表現し、関連性の強さを直感的に把握できます。
例えば、スポーツウェアの購入理由に関するアンケートで、「デザイン」「価格」「機能性」などの項目と、回答者の年代や性別との関係を分析する場合、コレスポンデンス分析を用いることで、各属性がどの要素を重視しているかを視覚的に示せます。
クラスター分析
「クラスター分析」は、多くのデータをクラスター(同じまたは類似性のあるもののグループ)に分類して分析する方法です。例えば、顧客満足度調査の結果をクラスター分析することで、満足度の高いグループと低いグループを特定し、「〇〇を購入している」「〇〇のサービスを利用している」などの特徴を明らかにします。大きく「階層クラスター分析」と「非階層クラスター分析」に分けられます。
階層クラスター分析
「階層クラスター分析」では、最も似ているクラスター同士を集め、次にそのまとまり同士を集め、という作業を繰り返し、大きなクラスターへと階層的にまとめていく方法です。樹形図にまとめることで過程が視覚的にわかりやすくなりますが、クラスターが多い場合は計算が複雑になります。
非階層クラスター分析
「非階層クラスター分析」では、あらかじめ決定したクラスター数にデータを分類します。K-means法が代表的な手法です。
アソシエーション分析
「アソシエーション分析」は、データ間の関連性を見つけ出す分析方法です。例えば、利用したサービスと満足度の関連性を探り、「〇〇を利用した人は満足度が高い」といった法則を見つけ出します。
時系列分析
「時系列分析」は、時間の経過に伴うデータの変動を分析します。季節性やトレンドを把握でき、今後の予測を立てることに適しています。例えば、月ごとの顧客満足度の変動を分析することにより、特定の季節に満足度が変化する原因を探ることができます。
自由記述の分析
自由記述の分析では、回答が「数値」の場合と「テキスト」の場合があり、分析方法が異なります。それぞれの方法について解説します
数値の場合
自由記述回答の数値情報は、平均値、中央値、標準偏差値、最小値、最大値などを算出します。数値の範囲が広い場合、一般的によく使われる平均値のみを見ると誤った考察をしてしまうことがあります。分析の精度を高めるために各値を算出することが重要です。
テキストの場合
自由記述回答がテキストの場合には、回答内容を意味のある単位に整理し、傾向を読み解くための手法が必要です。代表的な方法としては、「アフターコーディング」と「テキストマイニング」があり、目的や分析の深さに応じて使い分けられます。
ここでは簡単にご紹介し、詳しい手法や実務での活用方法については、後ほど解説します。
アフターコーディング:自由記述の回答をテーマ別に分類し、カテゴリごとに集計する方法です。
テキストマイニング:自然言語処理を使って、頻出キーワードや感情の傾向などを自動的に抽出する方法です。
自由記述アンケートの集計・分析方法について深掘り!
先ほどは、自由記述式アンケートの分析方法について、数値データとテキストデータの基本的なアプローチをご紹介しました。
自由記述形式のアンケートは、回答者の生の声を収集できる一方で、その集計や分析には特有の手法と工夫が求められる点が特徴です。
こちらでは、より実務に即したかたちで、代表的な4つの集計・分析手法をピックアップし、具体的な活用方法を解説していきます。
Excelを活用した手動集計
Excelは、自由記述データの整理と初歩的な分析に適したツールです。回答内容を一覧表にまとめ、フィルタリングや並べ替えを行うことで、特定のキーワードの出現頻度や傾向を把握できます。
また、ピボットテーブルを使用すれば、属性ごとの集計やクロス集計も可能です。ただし、大量のデータを扱う場合や詳細な分析を行う際には、他の手法との併用が望ましいです。
▼「Excelを活用したアンケートのまとめ方」についての詳しい記事はこちら

アフターコーディングによる分類と定量化
アフターコーディングは、自由記述の回答を共通のテーマやカテゴリに分類し、数値化して扱うための手法です。これにより、定性的なデータも定量的に集計・分析することが可能になります。
例えば、「サービスに関するご意見をお聞かせください」という設問に対して、回答内容を「価格」「品質」「対応」などのカテゴリに分類し、それぞれの出現頻度を数値化して整理します。
実際の運用では、回答内容をあらかじめ定めた分類基準に従って読み取り、共通するテーマや傾向に沿って整理します。「サービスの改善点」「好きなポイント」「使いやすさへの評価」など、意味の近い表現を同じカテゴリにまとめて扱うことで、全体の傾向や代表的な意見を視覚化できます。
ただし、すべての回答を目視で確認しながら分類コードを付与する必要があるため、手間と時間がかかります。そのため、あらかじめ分類基準を明確にしておくことが、効率的かつブレのない集計を行ううえで重要です。
テキストマイニングによる自動分析
テキストマイニングは、自由記述のような自然言語のデータを、専用ツールや自然言語処理技術を用いて分析する方法です。人の手では難しい大量のテキストデータを、短時間で効率的に処理するのに適しています。
分析では、文章を単語や文節に分解する「形態素解析」を行い、頻出する単語の抽出や、単語同士の関連性(共起関係)を可視化します。これにより、回答全体の傾向や特徴的なキーワードが浮き彫りになり、どのような話題が多く語られているか、どんな印象を持たれているかを把握できます。
例えば、ある商品のアンケート回答から「丁寧」「迅速」「待ち時間」などの単語が頻出した場合、これらが利用者にとって重要な要素であることが示唆されます。また、ポジティブ・ネガティブといった感情の傾向を分析する「感情分析」に応用することも可能です。
分析に使用するツールによっては、誤字や類義語の処理が弱い場合もあるため、結果を鵜呑みにせず、意味の読み取りや前処理にも注意を払う必要があります。
外部ツールとの連携による自動化
アンケートフォームを作成できる外部ツールを活用することで、自由記述データの収集から集計までを自動化が可能です。これらのツールは、回答データをリアルタイムで集計し、グラフ化する機能を備えています。
また、CSV形式でのデータ出力やGoogleスプレッドシートとの連携も可能で、さらなる分析や報告書作成が容易になります。初めてアンケート分析を行う方や、迅速なレポート作成が求められる場合に特に有効です。
自由記述式のアンケートは、回答者の深層心理や具体的な意見を把握するのに有効な手段です。適切な集計・分析手法を選択し、目的に応じて活用することで、より有益な情報が得られるでしょう。上記の方法を参考に、自社のニーズに合った分析手法を検討してみてください。
アンケート分析を効果的に行うためのポイント
アンケート分析を効果的に行うためのポイントを解説します。
分析目的の明確化
分析を始める前に、目的を明確にしましょう。アンケート調査自体の目的・目標に応じてどのような情報を得たいのか、どのように結果を活用するのかを具体化しておくことで、分析の方向性が定まりやすく、結果を効果的に活用できます。
アンケートデータの整理と前処理
データの整理と前処理は、分析の精度を高めるために重要です。具体的には、未回答によるデータの欠損部分の補完や、ミスとみられる異常値の除去などの作業があります。分析前にしっかりと前処理を行うことで、信頼性の高いデータを得ることができます。
全体像の把握
細かな分析を行う前にデータの全体像から把握していくことで、重要なポイントやトレンドを見逃しにくくなります。
グラフ等を用いた視覚的な分析
グラフ等を用いることで、データの傾向や関係性を直感的に理解しやすくなり、そこから立てた仮説を元にして、さらに深堀りした分析を行うことができます。
相関関係を把握する
アンケート分析では、各設問や評価項目の間にどのような関係性があるかを意識することが重要です。例えば、「スタッフの対応が良い」と評価した回答者が「全体の満足度も高い」と答えている場合、これらの項目間には関連性があると考えられます。
このような関連性を把握することで、単なる個別の数値の羅列ではなく、データ全体の中でどの要素が他の要素に影響を与えているのかを理解しやすくなります。結果として、より効果的な改善策や施策の立案につながるでしょう。
分析結果のまとめ方の注意点
分析結果をグラフなどにまとめる時の注意点を2つ紹介します。分析担当者以外にも分かりやすい形でまとめることで、活用方法についてのより効果的な議論につながるでしょう。
適切な種類のグラフを選ぶ
分析結果をより効果的に伝えるためには、適切なグラフを選ぶことが重要です。一般的に用いられるグラフの特徴を紹介します。
棒グラフ
「棒グラフ」は、各カテゴリの値を棒の長さで表現するグラフで、選択肢ごとの回答数や割合の比較に適しています。例えば、店舗ごとの満足度評価の平均値を比較するのに利用できます。
円グラフ
「円グラフ」は、円全体を100%として、各部分の割合を扇形の面積で視覚化するグラフです。割合を一目で理解しやすいため、構成比をグラフ化する時に適しています。例えば、総合評価に対する「非常に満足」「満足」「普通」「不満」「非常に不満」の回答割合を示すのに利用できます。
帯グラフ
「帯グラフ」は、棒グラフの一種です。帯全体を100%とし、各部分の割合を長方形の面積で視覚化するグラフです。円グラフと比べ、複数の項目を上下に並べて比較しやすいため、構成比を比較したいデータが多い時に適しています。例えば、総合評価の回答割合を年代別に示すのに利用できます。
折れ線グラフ
「折れ線グラフ」は、横軸に月や年などの時間経過、縦軸に数や割合をとり、各データの点を時系列に沿って線で結んでいくグラフです。折れ線の傾きで増加・安定・減少などの傾向がわかるため、時間の経過に伴うデータの傾向を把握するのに適しています。例えば、月ごとの総合評価の推移を示すのに利用できます。
散布図
「散布図」は、2つの変数を縦軸と横軸にとり、各データの点をとることで変数間の関係を視覚化するグラフで、「分布図」とも言います。グラフ上にデータの数だけ点が打たれ、因果関係や相関関係を示すのに適しています。例えば、「サービスの質」と「再来店意向」の関係を示すのに利用できます。
デザインやデータの順番を調整する
アンケートの分析結果を効果的に伝えるためには、資料のデザインやデータの順番を調整することも重要です。グラフの並び順を昇降順に並び替えたり、適切なタイトルやラベルを付けることで、グラフの内容をより明確に伝えることができます。ただし、デザインによってデータの誤認が起こらないように注意することも大切です。同じグラフ内の色は同系色にまとめる、データのスケールにも気を配るなどで、データを正確に解釈できるようにまとめましょう。
アンケートなら国内最大級のダイレクトリサーチサービス『ユニーリサーチ』
国内最大級のダイレクトリサーチサービス 「ユニーリサーチ」では、2,800万人の大規模パネルに対して最短即日かつリーズナブルなアンケート調査が可能です。
マニュアルが要らないシンプルな画面ですぐにアンケートが作成でき、初期費用・月額費用不要、1名、1問、10円〜のわかりやすい料金体系で数千円からアンケートを実施できます。性別、年齢、職業、世帯年収などの9つの属性でのセグメント配信や事前設問によるスクリーニングも可能です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。












