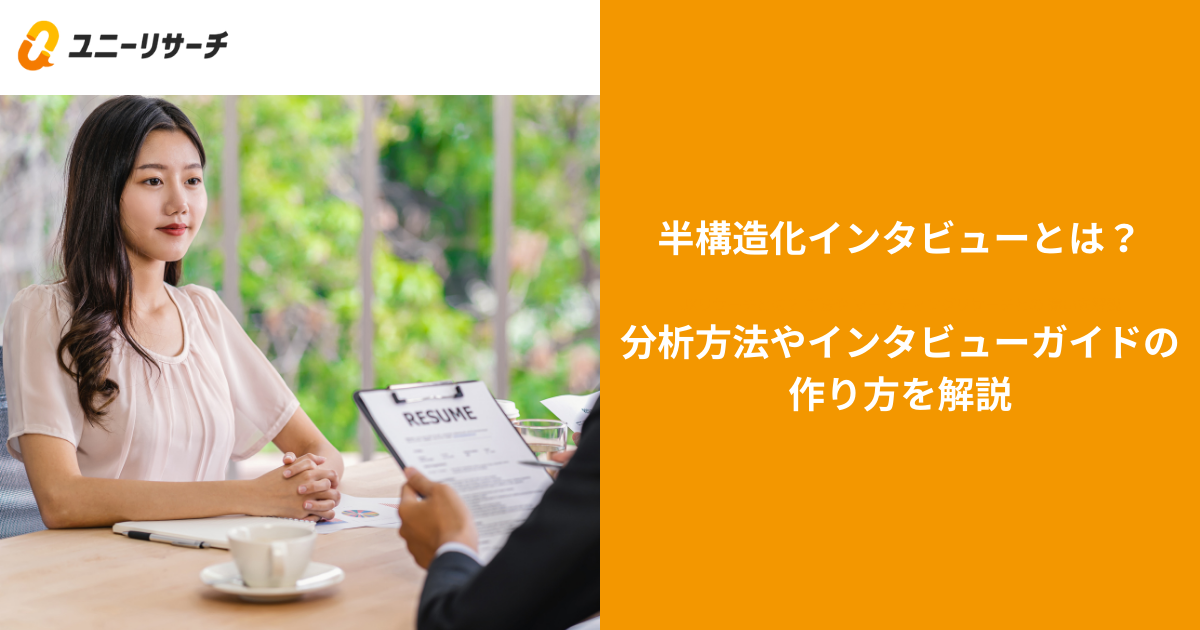
半構造化インタビューとは?分析方法やインタビューガイドの作り方を解説
「半構造化インタビュー」は、構造化された質問と、回答をより深堀りするための追加質問とを組み合わせることで、回答者の本音や潜在的なニーズを探りやすくなるインタビュー手法です。 この記事では、半構造化インタビューと他のインタビュー形式との違いやメリット・デメリット、成功させるための注意点とコツなどを解説します。
- 半構造化インタビューとは?
- 半構造化インタビューと構造化インタビューの違い
- 半構造化インタビューと非構造化インタビューの違い
- デプスインタビュー・グループインタビューとの関係
- インタビューガイドの作り方
- 調査目的を明確にする
- メインとなる質問を決める
- 深堀りするための質問を想定する
- 質問の順序や形式を検討する
- インタビュアー間で共有し、内容をブラッシュアップする
- 半構造化インタビューの質問例
- あらかじめ用意しておく質問
- 回答次第で追加・変更する質問
- 半構造化インタビューの分析方法
- 半構造化インタビューのメリット
- 回答に応じた柔軟な質問ができる
- 質的情報が得やすい
- 調査目的から脱線しても修正しやすい
- 半構造化インタビューのデメリット
- インタビュアーのスキルに結果が左右される
- インタビュアーの先入観が影響する可能性がある
- 質問が増えると時間がかかる
- 半構造化インタビューを成功させるための注意点とコツ
- 調査の目的を明確にする
- インタビュアーの選定が重要
- インタビュアーの主観を入れない
- オープンエンド型・クローズエンド型の質問を使い分ける
- 半構造化インタビューの回答者募集なら国内最大級のダイレクトリサーチサービス『ユニーリサーチ』
半構造化インタビューとは?
「半構造化インタビュー」とは、あらかじめ用意した質問項目(インタビューガイド)に沿いながらも、回答内容に応じて柔軟に質問を追加・変更していくインタビュー手法のことです。 あらかじめ決められた質問と、場の流れに合わせて追加する質問とを両立させることで、効率的に必要な情報を集めながら、回答者(インタビュイー)の深層心理や潜在的な行動要因も探りやすくなります。 ▼「インタビュー調査」についてのより詳しい記事はこちら

半構造化インタビューと構造化インタビューの違い
「構造化インタビュー」は、事前に質問項目や質問の順序、回答形式を厳密に定めた上で実施します。大規模な定量調査にも使用しやすく、回答の比較がしやすいのがメリットです。一方で、事前に用意した質問しか使用できないため、回答内容に対する深堀りができないというデメリットがあります。 「半構造化インタビュー」では、回答者の意見を掘り下げることができるため、新たな洞察を得られる点が大きな魅力です。ただし、インタビュアーの質問の展開力によって、得られる情報の量や質が大きく変わる可能性があります。
半構造化インタビューと非構造化インタビューの違い
「非構造化インタビュー」は、質問の順番や具体的な内容をあらかじめ決めず、回答や話しやすい内容に合わせて、その場で質問を考えていく手法です。自由度がとても高く、時間内に半構造化インタビューよりも深い情報を得られる可能性がありますが、その質はインタビュアーの経験と技量に大きく依存します。 「半構造化インタビュー」は、事前に決めた質問項目があるため、調査の目的から大きく逸脱しにくいというメリットがあります。高い自由度を確保したい場合には非構造化インタビューのほうが適していますが、調査の狙いを明確に持ちながら柔軟性も確保したい場合には、半構造化インタビューが適しているでしょう。
デプスインタビュー・グループインタビューとの関係
「デプスインタビュー(Depth Interview)」は1対1の対話形式で質問を重ねながら会話を深く掘り下げていくインタビュー形式です。「デプス(depth)」は深さや奥行きを意味します。回答者ごとに柔軟な対応が必要なため、半構造化インタビューまたは非構造化インタビューを用います。 共通した属性をもつユーザーのグループ(フォーカスグループ)を2つ以上作り、座談会形式でインタビューを実施する「フォーカスグループインタビュー(Focus Group Interview)」でも、半構造化インタビューまたは非構造化インタビューを用いることができます。半構造化インタビューを用いる場合、参加者同士の対話や反応を通して多様な意見を引き出していく妨げとならないような質問設計が必要です。 ▼「デプスインタビュー」についてのより詳しい記事はこちら

▼「フォーカスグループインタビュー」についてのより詳しい記事はこちら

インタビューガイドの作り方
半構造化インタビューを成功させるためには、「インタビューガイド」が重要です。調査の目的から逸脱しないようにするためのインタビューガイドの作り方を解説します。
調査目的を明確にする
まずは、今回のインタビューで明らかにしたいテーマや課題を洗い出し、目的を明確化します。目的が曖昧なままだと、質問が拡散してしまい、最終的に分析が難しくなります。
メインとなる質問を決める
調査目的に直結する質問を用意します。例えば、新商品の利用意向を探るのであれば「現在の類似商品に対してどういった点を重視するか」「商品を利用する際の不満はあるか」といった質問が考えられます。
深堀りするための質問を想定する
メインとなる質問への回答に対して、さらに掘り下げるためのサブ質問も用意しておきます。「なぜそう思ったのか」「具体的にはどのような経験があったか」など、自由な回答を引き出す質問や背景を確認する質問をあらかじめ書き出しておきます。
質問の順序や形式を検討する
半構造化インタビューでは、あらかじめ質問の順序を完全に固定しないこともありますが、最初は答えやすい質問から始め、徐々に深い内容へ進むことでスムーズなやりとりを促します。オープンエンド型・クローズエンド型の質問の使い分けも計画しておきましょう。
インタビュアー間で共有し、内容をブラッシュアップする
チームで調査を行う場合は、インタビュアー同士でガイドを共有して意見を出し合い、インタビューの流れや表現を調整します。 ▼「インタビューガイド」の作り方についてのより詳しい記事はこちら
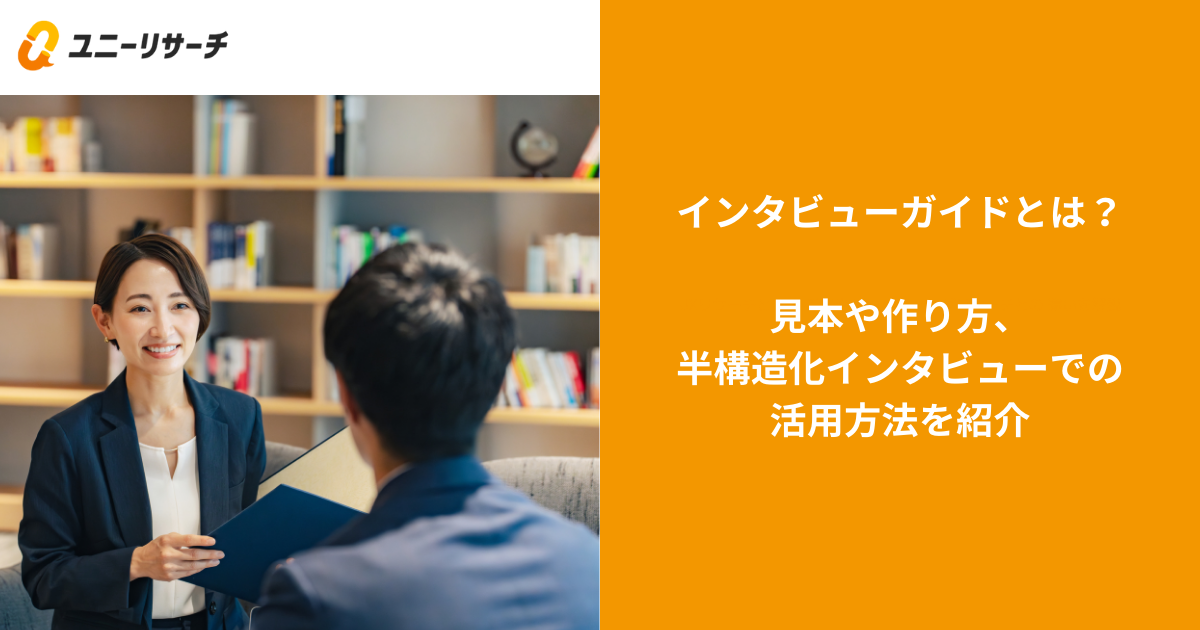
半構造化インタビューの質問例
半構造化インタビューであらかじめ用意しておく質問と回答次第で追加・変更する質問それぞれの例をご紹介します。
あらかじめ用意しておく質問
導入 「日常的に○○をどれくらい活用していますか?」 「今回のテーマである○○について、最初に浮かぶイメージは何ですか?」 評価・利用理由 「○○の使いやすい点・使いにくい点をそれぞれ挙げてください。」 「似た商品と比べて、どんな違いを感じますか?」 クロージング 「○○がもっと良くなるために必要だと思うことは何ですか?」 「話し足りないことや、付け加えたい意見があれば教えてください。」
回答次第で追加・変更する質問
理由や背景を掘り下げる 「どうしてそう感じたのですか?」 「具体的には、どんな場面や経験があったのでしょうか?」 理想・比較を探る 「理想的な○○とはどんなものですか?」 「他の選択肢と比べると、どこが一番大きな差だと思いますか?」 感情・動機を深める 「そのとき、どんな気持ちになりましたか?」 「それはどんなきっかけで生じましたか?」
半構造化インタビューの分析方法
半構造化インタビューの分析は、定性的なデータが中心となるため、回答内容をテキスト化(文字起こし)し、テーマ別に分類・要約していきます。具体的には、以下のような手順となります。 文字起こし:インタビュー録音や録画をもとにテキストに書き起こします。発言者が複数いる場合は、誰の発言かも明確にしておきます。自動文字起こしツールなどを用いると便利です。 コーディング:回答内容を読み込みながら、関連するテーマやキーワードにコードを付与していきます。たとえば「不満点」「サービス利用頻度」「購入の決め手」など、調査目的に沿った切り口で分類します。 カテゴリー化・マトリクス作成:コード化したデータをさらに抽象化し、カテゴリーごとに整理します。必要に応じて、マトリクスや表を用いて回答をまとめることで、共通点や傾向を把握しやすくなります。 考察・仮説の検証:整理したデータをもとに、調査前に立てた仮説が正しいのか、新たに発見した事実や洞察がどのような示唆を与えるのか、を分析します。複数の回答者間で共通する傾向や、少数派の興味深い意見をピックアップしながら考察を深めていきましょう。 レポート作成・共有:分析結果をグラフなどを活用したわかりやすい形でレポートにまとめ、関係者と共有します。定性的な調査結果は数字では表しにくい部分もあるため、具体的なエピソードや引用を添えて説得力を高めることも大切です。
半構造化インタビューのメリット
半構造化インタビューの主なメリット3つを紹介します。
回答に応じた柔軟な質問ができる
半構造化インタビューの最大の特徴は、質問の流れをある程度柔軟に変えられることです。回答者の興味や回答内容に合わせて追加質問で掘り下げることで、有益な情報を見逃すことなく拾える可能性が高まります。
質的情報が得やすい
あらかじめ設定した質問を基本にしつつ、回答者の反応に応じて自由に追加質問ができるため、回答者の本音や背景となる感情、価値観などの定量化しにくい情報を詳細に把握できます。
調査目的から脱線しても修正しやすい
非構造化インタビューほどではありませんが、半構造化インタビューでも話が脱線してしまうことがあります。半構造化インタビューではあらかじめ用意したインタビューガイドがあるため、調査目的から大きく外れた時にガイドラインに立ち戻りやすいというメリットがあります。
半構造化インタビューのデメリット
半構造化インタビューの主なデメリット3つを紹介します。
インタビュアーのスキルに結果が左右される
回答を引き出す力や、状況に応じて効果的な追加質問を行う技術など、インタビュアーのスキルが調査結果の質を大きく左右します。また、質問の順序や表現が適切でないと、回答者が答えづらくなり、重要な情報を引き出せない可能性があります。
インタビュアーの先入観が影響する可能性がある
回答を深掘りする過程で、インタビュアーの主観や先入観によって誘導的な質問となってしまうことがあります。先入観のない質問設計やインタビュー態度を保持することが重要です。
質問が増えると時間がかかる
回答者の答えを元に柔軟に質問を追加していくため、想定よりも質問数や所要時間が増えてしまうことがあります。必要な情報を得ながら所要時間内に終了できるような調査設計と時間管理が重要です。
半構造化インタビューを成功させるための注意点とコツ
半構造化インタビューを成功させるための注意点とコツを解説します。
調査の目的を明確にする
半構造化インタビューは自由度が高い一方で、目的やテーマが曖昧だと、回答が散漫になり分析が難しくなります。インタビューを行う前に、目的・ゴールを具体的に定義し、そのために必要な情報をリストアップして明確にしましょう。
インタビュアーの選定が重要
インタビュアーには、質問設計やファシリテーションの能力はもちろん、回答者に安心感を与えるコミュニケーションスキルが求められます。回答者の意見を否定しないことや、適切なアイコンタクト・相づちを行うことなど、相手が話しやすい雰囲気を作ることができるインタビュアーかどうかも重要です。
インタビュアーの主観を入れない
インタビュー中に「この商品、私も使っています」などのインタビュアーの共感や意見を強く押し出してしまうと、回答者がそれに沿った回答をする恐れがあります。インタビュアーはあくまで客観的な立場で質問を投げかけることを意識し、回答者の答えをじっくり聞く姿勢を保ちましょう。
オープンエンド型・クローズエンド型の質問を使い分ける
自由回答を引き出すオープンエンド型の質問は深い洞察を得るために効果的ですが、質問を限定するクローズエンド型の質問を挟むことで、回答を整理しやすくなります。両方をバランス良く組み合わせることで、より深みのある情報を得やすくなるでしょう。
半構造化インタビューの回答者募集なら国内最大級のダイレクトリサーチサービス『ユニーリサーチ』
「ユニーリサーチ」は、調査会社を介さずに「最短当日・従来調査費用の10分の1以下」での様々なリサーチを可能にする国内最大級のダイレクトリサーチサービスです。数万人の多様なユーザーにアプローチでき、基本属性の選定や事前設問によるスクリーニングで調査の目的に沿わないユーザーとのミスマッチを防止します。 「オンラインインタビュー」やオフラインでの「会場調査」「訪問調査」などのインタビュー募集にもご活用いただけます。2025年7月時点で、登録企業3,000社、累計リサーチ件数60,000件を突破した「ユニーリサーチ」をぜひこの機会にご検討ください。












