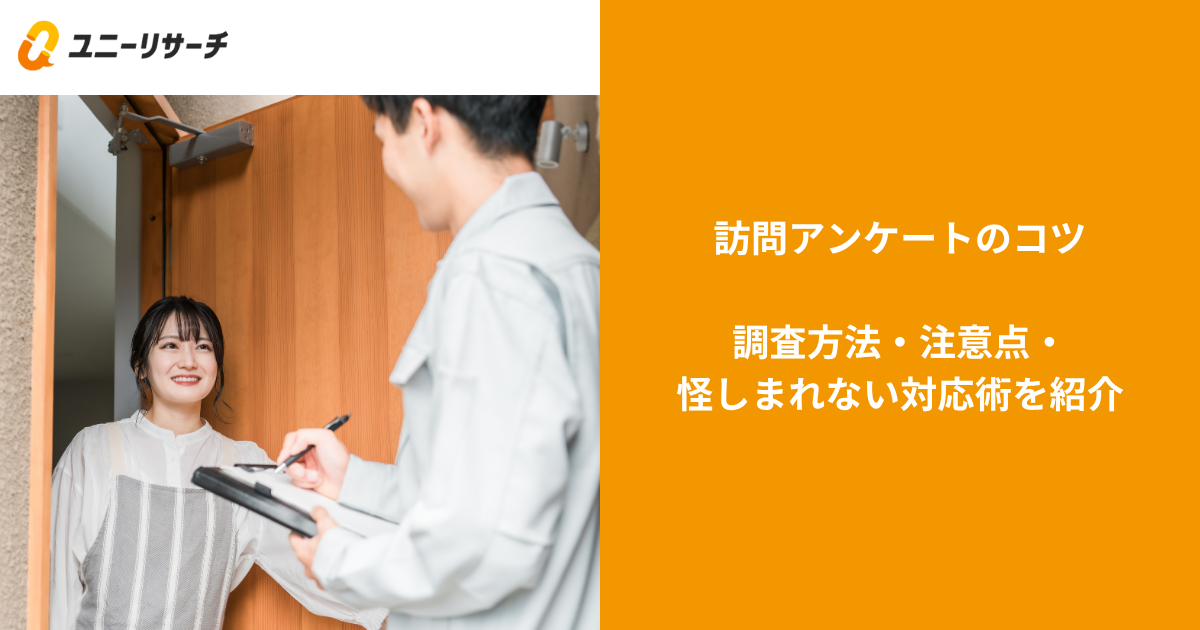
訪問アンケートのコツ|調査方法・注意点・怪しまれない対応術を紹介
「訪問アンケート」は、対象者の自宅や職場を直接訪れて情報を収集する調査手法です。対面ならではのリアルな反応や詳細な意見が得られる一方で、実施には配慮や準備が必要です。 本記事では、訪問アンケートの基本から、実施時の注意点、怪しまれず信頼を得るためのコツなどを解説します。
- 訪問アンケートとは?
- 訪問アンケートの目的
- 訪問アンケートのメリットとデメリット
- 訪問アンケートのメリット
- 訪問アンケートのデメリット
- 訪問アンケートの調査方法と流れ
- STEP1:調査目的の明確化とターゲット設定
- STEP2:調査票(アンケート項目)の作成
- STEP3:調査員のリクルート・研修・マニュアル整備
- STEP4:訪問・調査の実施
- STEP5:調査結果の集計、分析
- 訪問アンケートの注意点
- 個人情報保護と倫理的配慮
- 訪問時間帯・地域への配慮
- トラブル時の対応フロー
- 怪しまれない訪問アンケートの3つのコツ
- コツ1. 第一印象で信頼を得る挨拶と身だしなみ
- コツ2. 不信感を抱かれない説明と質問の仕方
- コツ3. 身分証明・依頼状の提示で安心感を与える
- 訪問調査なら国内最大級のダイレクトリサーチサービス『ユニーリサーチ』
訪問アンケートとは?
「訪問アンケート」とは、調査員が対象者のもとを訪れ、口頭で質問しながら回答を得る訪問調査の一種です。紙や電子端末を使い、回答をその場で記録します。郵送やWEBとは異なり、質問に対する理解度を確認しながら進行できるのが大きな特徴です。 ユーザーの表情や反応を直接見ながら調査できるため、アンケートという定量的な調査方法でありながら、感情などの定性的な情報も収集しやすい特徴があります。 ▼「訪問調査」についてのより詳しい記事はこちら

▼「アンケート調査」についてのより詳しい記事はこちら
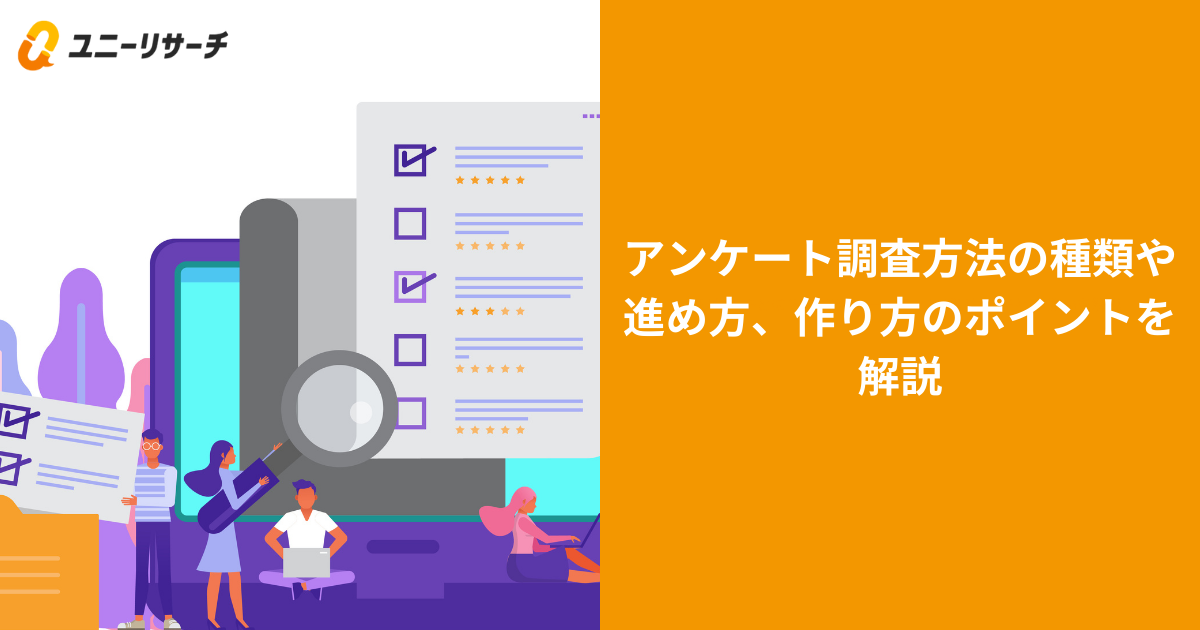
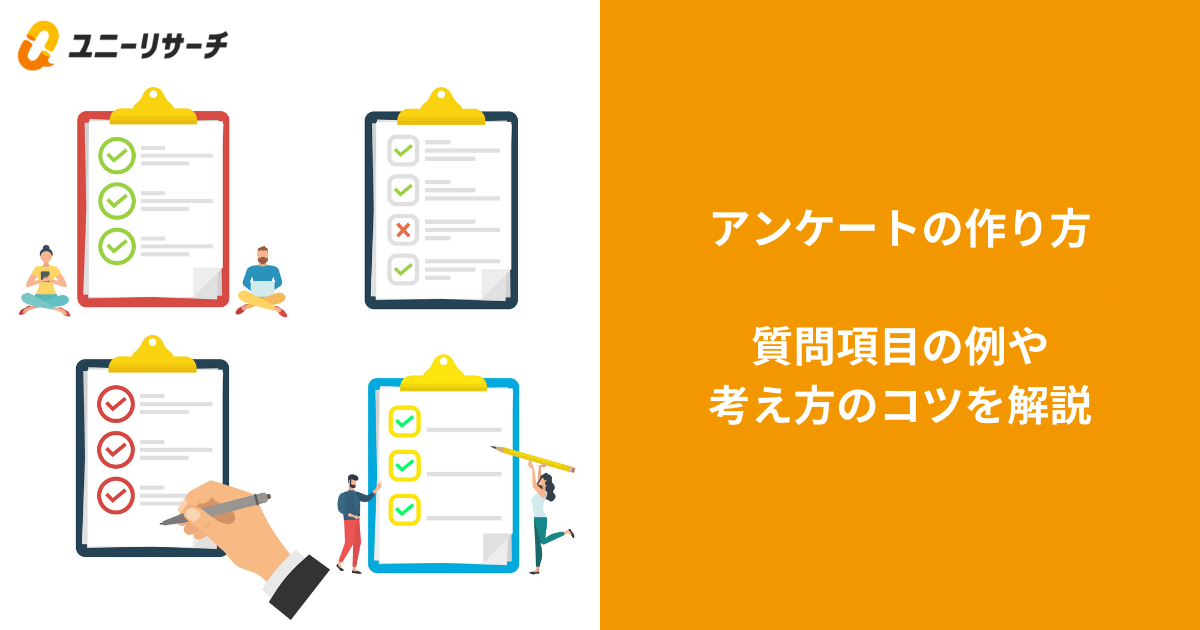
訪問アンケートの目的
訪問アンケートは、対面で回答を得るため、WEBや電話調査では得られにくい「生の声」や、非言語的な反応(表情・態度)を観察できる点が強みです。特に年配層やインターネット非利用者を対象とする場合に向いています。
訪問アンケートのメリットとデメリット
訪問アンケートは、対象者と直接対話できることから、高度な情報収集が可能な一方で、実施における負担も大きい手法です。以下に、企業の調査における主なメリットとデメリットを整理して紹介します。
訪問アンケートのメリット
深いインサイトを得られる:対面で調査を行うため、表情や雰囲気などの非言語情報も把握しやすく、深いインサイトが得られます
質問意図の誤解を防げる:その場で補足説明ができるため、質問の意図を正確に伝えることができます
高い回答率が期待できる:対面で時間を確保して行うため、電話や郵送よりも回答率が高い傾向にあります
インターネット非利用層にも対応可能:高齢者など、インターネットを利用しない層にアプローチする手段として有効です
自由記述の質が高い:話し言葉で自然に情報を引き出せるため、自由回答の内容が具体的になりやすいです
訪問アンケートのデメリット
コストと人手がかかる:調査員の人件費・交通費などの実施コストがかかります
実施範囲が限られる:物理的に訪問できるエリアに限定されるため、規模が大きくなればその分多くの予算が必要です
対象者に心理的負担を与える可能性がある:突然の訪問に警戒されたり、プライバシーの侵害と受け取られたりするリスクがあります
調査員のスキルに依存する:調査員の対応の良し悪しで回答内容や調査の信頼性が左右されやすい点に注意が必要です
スケジュール調整の手間:アポイント型の場合、対象者との日程調整に時間を要することがあります
訪問アンケートの調査方法と流れ
訪問アンケートには、「飛び込み型」と「事前アポイント型」の2つの方法があります。飛び込み型は広範なサンプルを確保しやすい一方、拒否されるリスクも高くなります。事前アポイント型は先に訪問許可を得ているため拒否されにくく、効率的に実施できる一方、日程調整の手間がかかります。 訪問アンケート調査の基本的なステップを5段階で紹介します。
STEP1:調査目的の明確化とターゲット設定
まずは、調査の目的を明確にします。たとえば「新商品の認知度を把握したい」「地域住民の生活実態を知りたい」など、調査で得たい情報を具体化しましょう。そのうえで、調査対象となる年齢層・性別・地域などの条件を設定します。
STEP2:調査票(アンケート項目)の作成
目的に沿って、具体的な質問を設計します。質問は短く、回答しやすい表現にすることがポイントです。Yes/Noや5段階評価などの定量項目に加えて、自由記述欄を設けることで、より深い意見を引き出すことが可能です。 また、質問の順番にも工夫を加え、スムーズな流れで答えられる構成にしましょう。質問は、誘導的にならないように留意します。
STEP3:調査員のリクルート・研修・マニュアル整備
調査員には信頼感ある態度と正確な記録力が求められます。企業内のスタッフでも外部委託でもかまいませんが、どちらの場合も統一的な対応ができるように研修を行います。訪問時の挨拶、質問の読み上げ方、トラブル対応までを網羅したマニュアルを用意し、実地訓練なども行うのがおすすめです。
STEP4:訪問・調査の実施
調査エリアやスケジュールを決め、実際の訪問を行います。事前アポイント型であれば、事前に電話連絡や郵送案内を行い、了承を得たうえで訪問します。調査当日は、身分証明書や依頼状の提示、自己紹介のあとに質問を開始し、回答内容をその場で正確に記録します。拒否された場合の対応フローも事前に決めておきましょう。
STEP5:調査結果の集計、分析
訪問後は、調査票やデジタル記録を集計・整理します。データの誤入力を防ぐため、ダブルチェック体制を整えるのが理想です。集計後は、グラフ化やクロス集計などの手法で分析し、傾向を把握します。最後に、調査結果を報告書としてまとめ、関係者に共有します。
訪問アンケートの注意点
訪問アンケートでは、以下の項目に注意しましょう。
個人情報保護と倫理的配慮
訪問アンケートでは、調査対象者の個人情報を扱うため、個人情報保護法に基づく対応が必須です。調査開始時には、実施主体・目的・使用範囲などを丁寧に説明し、同意を得る必要があります。また、調査結果は特定の個人が識別されない形で活用・報告することを徹底しましょう。調査票や記録にも適切な管理が求められます。 参考:「個人情報保護法」を分かりやすく解説。個人情報の取扱いルールとは? | 政府広報オンライン
訪問時間帯・地域への配慮
訪問時間は、生活リズムや地域性を考慮することが大切です。早朝・夜間・休日の訪問は避け、平日の午前10時から夕方5時までを目安とします。集合住宅では管理規定の確認も必要です。 ただし、仕事などの関係で日中不在にする場合も考えられるため、事前アポイントを行うのも効果的です。地域によっては訪問に対する警戒感が強い場合もあり、自治体や地域団体に事前連絡しておくとスムーズに進みやすくなります。
トラブル時の対応フロー
訪問中に拒否やクレームが発生した場合の対応も想定しておきましょう。調査員には、冷静かつ丁寧に謝意を伝えるよう指導し、無理な調査継続は絶対に避けます。また、トラブルが発生した場合は、速やかに上司または本部に報告し、再発防止に努めるフローを整えておきましょう。
怪しまれない訪問アンケートの3つのコツ
初対面の訪問者には不信感を抱かれることが少なくありません。怪しまれないために、以下のことに気を配りましょう。
コツ1. 第一印象で信頼を得る挨拶と身だしなみ
調査員の印象は、アンケートへの協力度に大きく影響します。清潔な服装、丁寧な言葉遣い、名刺の提示など、第一印象に配慮することが大前提です。特に、訪問直後の挨拶は重要で、「○○会社から調査に伺いました。ご迷惑でなければ○分ほどお話を伺ってもよろしいでしょうか?」など、丁寧で具体的な説明が効果的です。
コツ2. 不信感を抱かれない説明と質問の仕方
「この人は本当に調査員か?」「どこに情報が使われるのか?」といった不安を払拭するには、説明力が不可欠です。調査の目的・所要時間・個人情報の扱いについて、簡潔かつ明確に伝えましょう。また、質問の進行も自然な会話の流れを意識し、一問一答ではなく双方向的なやり取りが安心感を生みやすくなります。
コツ3. 身分証明・依頼状の提示で安心感を与える
調査員は必ず身分証明書を携帯し、ユーザーの要望があればすぐ提示できるようにしておくことが重要です。加えて、依頼元企業名や調査目的を記載した説明書やパンフレットも持参しましょう。訪問前に配布して地域住民に周知してもらうことで、「知らない人が来た」という不信感を減らすこともおすすめです。
訪問調査なら国内最大級のダイレクトリサーチサービス『ユニーリサーチ』
「ユニーリサーチ」は、調査会社を介さずに「最短当日」でリサーチを開始でき、コストは「従来の10分の1以下」に抑えることが可能な国内最大級のダイレクトリサーチサービスです。数万人規模の多様なユーザーにアクセスでき、基本属性や事前質問によるスクリーニングにより、目的に合わない対象者とのミスマッチを防げます。 スタートアップ企業や大手企業の新規事業部門など、従来の調査サービスを十分に活用できていなかった層を中心に導入が進み、2025年7月時点で登録企業は3,000社、累計リサーチ件数は6万件を突破しました。この機会に、スピーディかつ柔軟なリサーチを実現する「ユニーリサーチ」をぜひご活用ください。












