
顧客満足度調査のやり方や目的は?アンケートサンプル(質問項目)や成功のポイントを解説
顧客との良好な関係を築くことは、企業の成長を考える上で欠かせません。その関係性の指標として活用されているのが「顧客満足度調査」です。
本記事では、顧客満足度調査の概念から、代表的な調査指標やKPI、具体的な質問項目のサンプルなどを解説します。
- 顧客満足度調査とは?
- 顧客満足度調査の目的
- 商品やサービスの改善への活用
- 信頼性や顧客ロイヤルティの向上
- リピーターの獲得
- 顧客満足度調査で使われる代表的な指標
- 顧客満足度指数(CSI)
- 日本版顧客満足度指数(JCSI)
- CES(顧客努力指標)
- NPS®(Net Promoter Score)
- 顧客満足度向上のためのKPI
- LTV(顧客生涯価値)
- 顧客維持率(CRR)
- 解約率(チャーンレート)
- 顧客紹介数
- 顧客満足度調査の方法・手順
- 顧客満足度調査のサンプル|アンケートの質問項目
- 顧客満足度調査を成功させるポイント
- シンプルで答えやすい質問を設計する
- 偏りのないデータ収集を意識する
- 調査結果を社内全体にフィードバックする
- 継続的に調査し改善につなげる
- 顧客満足度を向上させるには?
- 期待を超える価値を提供する
- 顧客の声を活かし関係を深める
- 業務オペレーションを最適化する
- 従業員満足度を高める
- 顧客満足度調査に国内最大級のダイレクトリサーチサービス『ユニーリサーチ』
顧客満足度調査とは?
「顧客満足度調査」とは、製品やサービスを利用した顧客が「どの程度満足しているのか」を測定し、その背景となる要因や改善点を明らかにするための調査手法です。
満足度については、アンケートやレビューを通じて、「とても満足」「満足」などの肯定的な回答と、「不満」「とても不満」といった否定的な回答の割合を比べて、満足度を数値化します。アンケートなどの定量調査とインタビューなどの定性調査を組み合わせて満足度の背景も探ることで、製品・サービスの具体的な魅力や課題を把握できます。
顧客満足度調査の目的
企業が顧客満足度調査を行う目的を3つご紹介します。
商品やサービスの改善への活用
顧客が実際に商品を利用する中で感じていることが、企業が想定していたものと異なるケースも多くあります。顧客満足度調査で得たフィードバックをもとに改善を行うことで、より顧客のニーズにマッチした製品・サービスに進化させることが可能です。
信頼性や顧客ロイヤルティの向上
顧客満足度調査の結果を活かして、サポート対応やブランド体験を強化することは、顧客の信頼感やロイヤルティを高め、企業イメージを大きく向上させる効果を期待できます。
リピーターの獲得
調査結果を活かして顧客満足度を向上できれば、リピート率や顧客維持率が高まり、結果として企業の収益基盤を強固にすることができます。多くの既存顧客がリピーターとなれば、企業は安定的に売上を確保でき、新規顧客獲得のためのマーケティングコストも抑えられます。
顧客満足度調査で使われる代表的な指標
顧客満足度調査で使われる4つの代表的な指標を紹介します。
顧客満足度指数(CSI)
「顧客満足度指数(CSI:Customer Satisfaction Index)」は、商品・サービスに対する総合評価を、複数の要素(価格、品質、デザイン、機能性など)に分解して測定し、合算することで算出する指標です。点数が高い要素があれば、どの点が顧客満足に寄与しているかが明確になります。逆に低いところは、改善することで顧客満足度を引き上げる余地があると判断できます。
日本版顧客満足度指数(JCSI)
「日本版顧客満足度指数(JCSI:Japanese Customer Satisfaction Index)」は、顧客満足度を日本国内の業種別に数値化し、ベンチマークとするための指標です。国内市場での自社ポジションを測る指標として、大手企業を中心に導入が進んでいます。
CES(顧客努力指標)
「CES(Customer Effort Score:顧客努力指標)」は、顧客が目的を達成するまでにどの程度の「手間」や「労力」を感じたかを評価する指標です。たとえば、購入手続きの煩雑さや問い合わせ時の長い待ち時間など、サービス利用時のストレス要因が高ければ満足度は低くなりやすいと考えられます。最近は「いかに簡単に利用できるか」を重視する傾向が強まっているので、購買体験やカスタマーサポートの改善に役立つ指標として、CESの重要性も増していると言えるでしょう。
NPS®(Net Promoter Score)
「NPS®(Net Promoter Score)」は、周囲に積極的に推奨してくれる「推奨者」の割合から「批判者」の割合を差し引いた値を示します。
「あなたはこの〇〇(商品、サービス、ブランドなど)をどの程度友人や知人に薦めたいと思いますか?」という質問をし、その回答を0~10点の11段階で評価してもらいます。
回答は以下の3つに分類されます。
9〜10点:推奨者(Promoters)
7〜8点:中立者(Passives)
0〜6点:批判者(Detractors)
数値が高いほど顧客エンゲージメントが強く、低いと不満が多い状態と判断できますが、国や業界ごとに基準値は異なります。日本は回答中心化傾向(評価尺度の真ん中よりの回答をする傾向。NPSで言えば5や6など)があり、低く出ることがよくあります。
▼「NPS調査」についてのより詳しい記事はこちら

顧客満足度向上のためのKPI
顧客満足度を高めることは、企業の収益拡大やブランド強化に直結します。しかし、それを定量的に把握するにはKPI(重要業績評価指標)を設定し、モニタリングを続けることが重要です。
KPIとして使用できる4つの指標を紹介します。
LTV(顧客生涯価値)
「LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)」は、一人の顧客が生涯にわたって企業にもたらす収益の総額を指します。
一般的な計算式のひとつは「LTV = 平均購入額 × 購入頻度 × 継続期間」です。
顧客満足度が高いほど、リピート購入やアップセル、クロスセルが発生しやすく、LTVが上昇する可能性が高くなります。顧客との長期的な関係維持は企業の売上の安定につながるため、最重要KPIにすることも少なくありません。
顧客維持率(CRR)
「顧客維持率(CRR:Customer Retention Rate)」は、一定期間内にどれだけの顧客と取引を継続できたかを示す割合です。定期購買(サブスクリプション)型ビジネスやSaaSにおいては特に、顧客維持率が高いほど収益が安定します。
解約率(チャーンレート)
「解約率(チャーンレート)」は、CRR(顧客維持率)と表裏一体の概念で、特定期間内にユーザーがサービスを辞める割合を示す指標です。
計算式は「解約率 = 特定期間内の解約したユーザー数 ÷ 特定期間の当初のユーザー数 × 100」です。
顧客満足度が低いと解約率が高くなる傾向があり、伴って顧客維持率は下がってしまいます。顧客は「なぜ解約に至ったのか」を調査し、その課題を解決する施策が必要です。解約率を下げることは、新規顧客を獲得するためのコストを抑えながら、売上を伸ばすうえでも重要な戦略です。
顧客紹介数
「顧客紹介数」とは、既存の顧客が友人や知人などに商品・サービスをどれだけ紹介しているかを示す指標です。「おすすめしたい」という推奨意向度はNPS調査で測定することができますが、実際に紹介した数も重要な指標となります。満足度の高い顧客ほど、積極的に周囲に勧める傾向があります。紹介プログラムを設計し、紹介数の推移をKPIとして把握することで、顧客満足度の変化を測定できるでしょう。
顧客満足度調査の方法・手順
顧客満足度調査を行う時は、まず「どんな情報を得たいか」「その結果をどのように活用したいか」を明確にし、カスタマージャーニー(顧客が商品やサービスを知ってから購入に至るまでの流れ)を整理して、どの時点で顧客満足度が左右されるかの仮説を立てます。
次に調査の方法を決定します。調査のタイミングとしては、長期的な顧客満足度の推移を見る「リレーショナル型」と、購入直後の印象を把握する「トランザクション型」のどちらを使うか、または組み合わせるかを検討します。方法面では、全体像をより立体的に把握できるようにアンケートなどで数値データを得る定量調査と、インタビューなどで顧客の感情や背景を深掘りする定性調査をバランスよく組み合わせることをおすすめします。
また、自社で調査を行う場合は金銭的なコストを抑えられますが、専門的なノウハウや社内リソースが必要となること、一方で、調査会社などの外部へ委託する場合は客観性を持った専門家の分析結果と効率が得られますが、費用が増えることにそれぞれ注意が必要です。調査会社を介さずに様々なリサーチを実施できるダイレクトリサーチサービスの利用もおすすめです。
調査方法が決定したら、設問を用意して調査を実施し、結果の集計・分析を行います。分析結果を社内の各部門で共有して改善策に反映させることが、顧客満足度を高める鍵となります。
▼「カスタマージャーニー」についてのより詳しい記事はこちら

顧客満足度調査のサンプル|アンケートの質問項目
シンプルな顧客満足度調査の質問項目のサンプルをご紹介します。
この商品・サービス全体の満足度を教えてください。(5段階評価)
最も満足している点・魅力だと思う点は何ですか?(自由回答)
不満や改善してほしい点があれば教えてください。(自由回答)
当社の商品・サービスをどの程度友人や知人に薦めたいと思いますか?(0~10点)
また利用したいと思いますか?(はい/いいえ)
その理由を教えてください。(自由回答)
(他社との比較が可能な場合)他社製品やサービスと比較して、優れている点・劣っている点はありますか?(自由回答)
その他、ご意見・ご要望があればご自由にお書きください。(自由回答)
ポイントは、回答を数値化しやすい定量的な項目と、顧客の本音や具体的なエピソードを引き出す定性的な項目をバランスよく配置することです。
▼「アンケート」についてのより詳しい記事はこちら
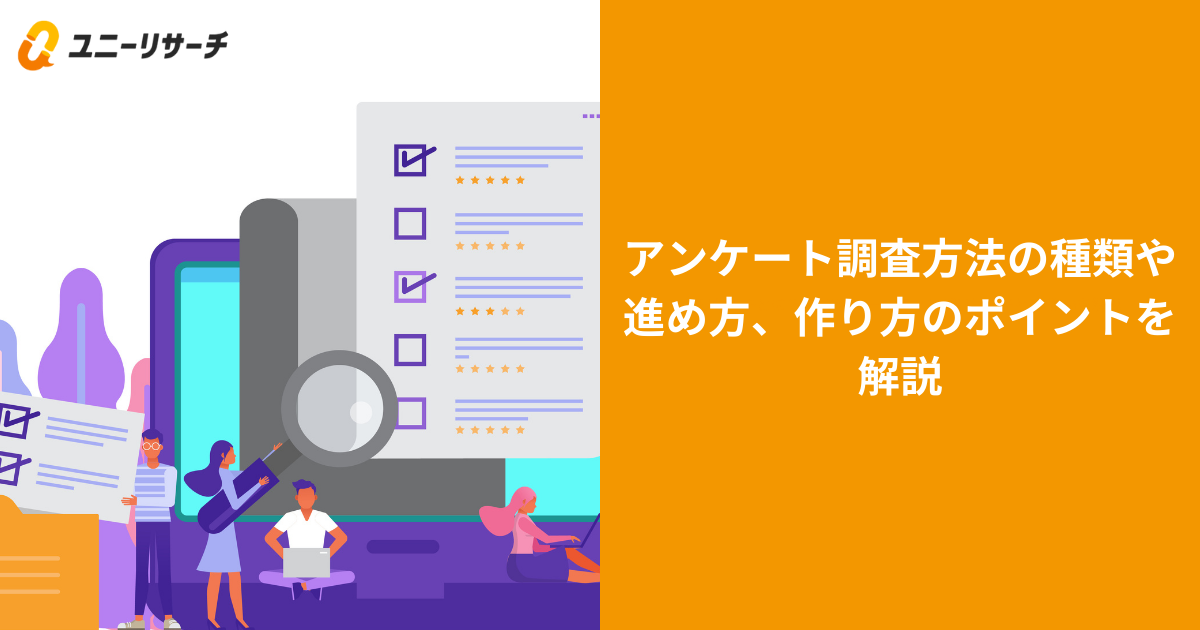
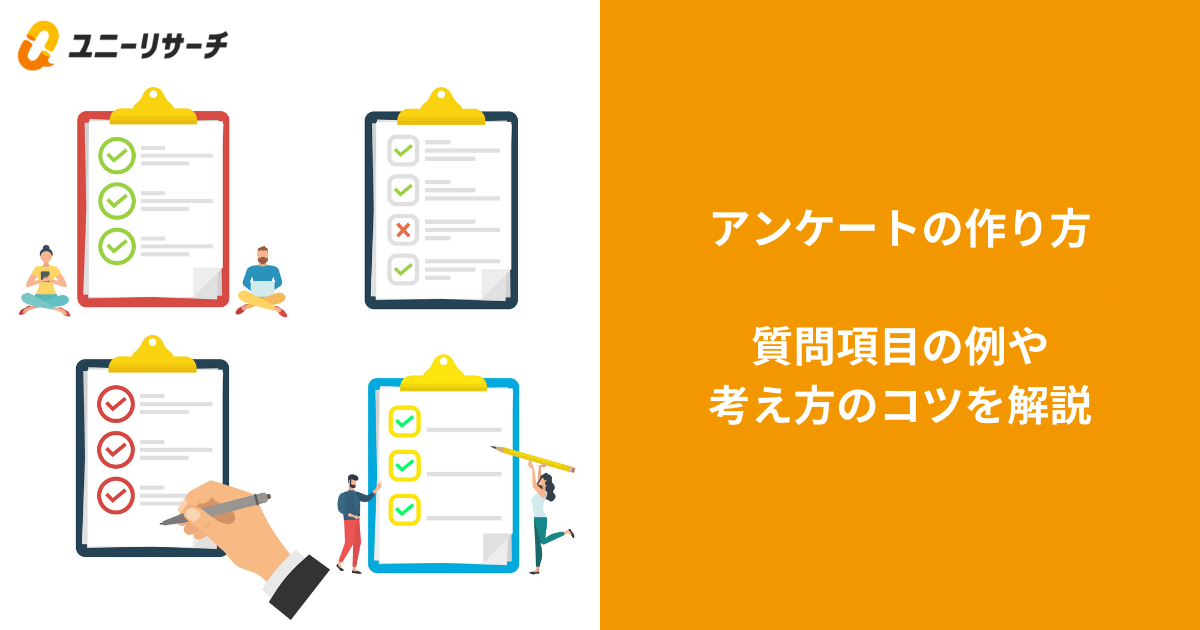

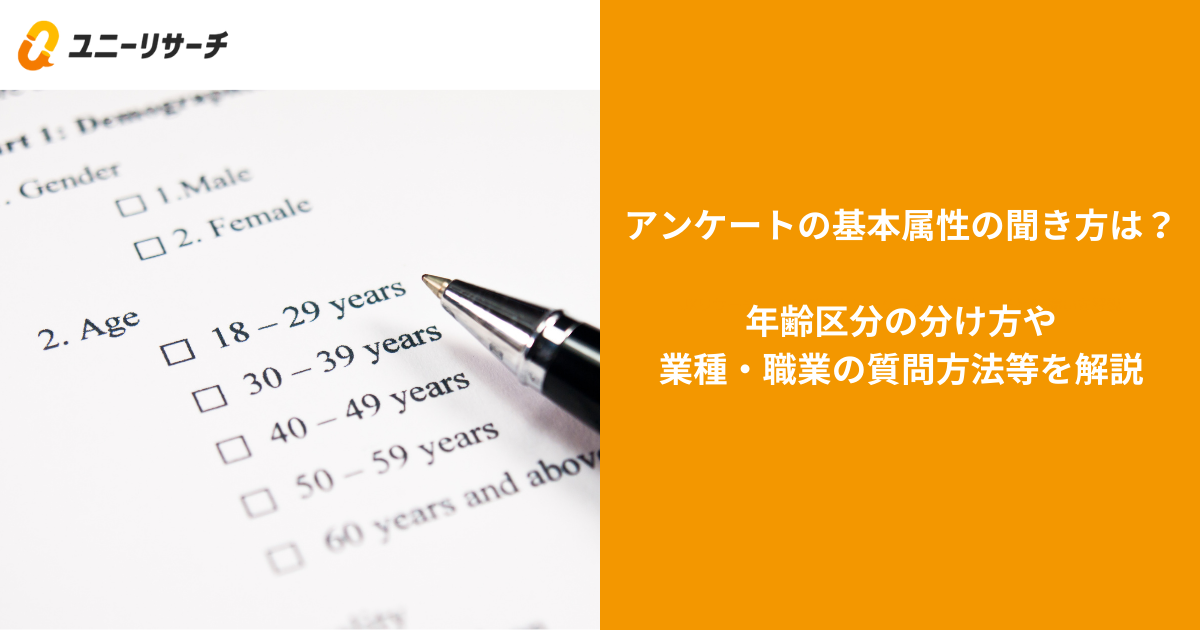
顧客満足度調査を成功させるポイント
顧客満足度調査を成功させるためのポイントを4つご紹介します。
シンプルで答えやすい質問を設計する
顧客満足度調査の設問が多すぎたり、一般的でない専門用語が入っていると、回答者は途中で離脱しやすくなります。質問をシンプルにまとめることで、回収率と回答の品質が向上します。
偏りのないデータ収集を意識する
自社のファンや特定の年代だけに偏った調査は、実際の顧客の全体像を正確に反映できません。複数のチャネルを使った募集や、実際の顧客属性の分布を意識したサンプリングなどによって、幅広い層から回答を得る工夫が必要です。
調査結果を社内全体にフィードバックする
顧客満足度調査のデータや分析結果は、マーケティング部門だけでなく、開発・営業・カスタマーサポートなどの他の部門でも共有するのがおすすめです。顧客の声を組織全体で真摯に受け止め、各部門が改善やサービス向上に取り組むことで、より一貫性のある顧客体験を提供できます。
継続的に調査し改善につなげる
顧客満足度は一度調査したら終わりではありません。ライフスタイルや市場環境の変化に応じて、顧客の求めるものは変化するため、定期的に調査を行って改善を続けていきましょう。
顧客満足度を向上させるには?
顧客満足度調査の結果を踏まえたうえで、具体的にどのような施策を行えば顧客満足度を向上できるのでしょうか。ここでは4つのアプローチを紹介します。
期待を超える価値を提供する
顧客は、購入前に何らかの期待を抱いています。その期待値を超える顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)を提供できれば、大きな満足感や感動を生み出すことができ、顧客満足度も向上するでしょう。
▼「顧客体験(CX:Customer Experience)」についてのより詳しい記事はこちら

顧客の声を活かし関係を深める
顧客満足度調査で集めた声をもとに、打ち出した改善策の内容や進捗を顧客へこまめに報告することで「自分の意見を大切にしてくれている」という印象を強化し、満足度向上につなげることができます。
業務オペレーションを最適化する
業務フローやシステムの最適化に取り組み、顧客が「ストレスなくスムーズに」利用できる環境を整えましょう。CES(顧客努力指標)の観点から見ると、このアプローチは特に効果が大きいです。
従業員満足度を高める
顧客との直接的な接点となる従業員の満足度が高く、モチベーションの高い状態であれば、顧客対応の質も向上するはずです。従業員満足度を高めることで、顧客満足度の向上も狙うことができます。
顧客満足度調査に国内最大級のダイレクトリサーチサービス『ユニーリサーチ』
「ユニーリサーチ」は、調査会社を介さずに「最短当日・従来調査費用の10分の1以下」での様々なリサーチを可能にする国内最大級のダイレクトリサーチサービスです。数万人の多様なユーザーにアプローチでき、基本属性の選定や事前設問によるスクリーニングで調査の目的に沿わないユーザーとのミスマッチを防止します。
「アンケート」や「オンラインインタビュー」などのリサーチサービスを利用した顧客満足度調査にもご活用いただけます。2025年7月時点で、登録企業3,000社、累計リサーチ件数60,000件を突破した「ユニーリサーチ」をぜひこの機会にご検討ください。












