
ユーザーエクスペリエンス(UX)の基礎知識とユーザー体験向上のコツ
「ユーザーエクスペリエンス(User Experience/UX)」は、ユーザーが商品やサービスを利用した時に得る知覚や反応などのすべての体験を指します。顧客満足度の向上やブランド価値の強化に直結する重要な要素であり、優れたUXを提供することは、ユーザーの信頼獲得や継続的な利用の増加につながります。
本記事では、ユーザーエクスペリエンス(UX)の基礎知識やCXやUIとの違い、UX向上のためのコツなどを解説します。
ユーザーエクスペリエンス(UX)とは?
「ユーザーエクスペリエンス(UX:User Experience)」とは、商品やサービスを利用する際にユーザーが得るすべての体験を指します。この「体験」には、使いやすさ(ユーザビリティ)だけでなく、感情的な満足度や商品やサービスとユーザーの長期的な関係性も含まれます。また、購入前に他の商品と比較する時、不具合が生じてアフターフォローを申し込む時、といった利用前後での体験もUXの一部です。
例えば、スマートフォンに料理レシピのアプリをダウンロードする場合、
料理を作りたいと考える →レシピアプリを探す →レシピアプリを選択し、ダウンロードする →アプリでレシピを探す →選んだレシピを元に料理を作る →作った料理を食べる →アプリの使いやすさやレシピの良さを感じて、また利用しようと思う
といった流れすべてがユーザーエクスペリエンス(UX)に入ります。
ユーザーエクスペリエンス(UX)が生まれた背景
ユーザーエクスペリエンス(UX)が生まれた背景には、産業革命以降の機械化と、それに伴う製品や市場の複雑化があります。機械製品の品質を追い求める中で、認知工学者のドナルド・アーサー・ノーマンは1988年にデザインと人間の認知の関係を分析した書籍『The Design of Everyday Things』(邦題:『誰のためのデザイン?―認知科学者のデザイン原論』)を発表し、製品設計におけるユーザー中心の考え方を広めました。
彼がAppleに在籍していた時、「ユーザーエクスペリエンス・アーキテクト」という役職を名乗ったことが、UXという概念の普及につながったと言われています。
その後、2000年代以降のスマートフォンやアプリの発展と普及に伴って、IT業界では直感的な操作性やユーザビリティが競争優位性を左右する重要な要素となったことが、現在のUXの概念へと発展していきました。
なぜユーザーエクスペリエンス(UX)が重要視されるのか
ユーザーエクスペリエンス(UX)が重視される具体的な背景として「顧客の価値観の多様化」と「デバイスの多様化」の観点から解説します。
ユーザーの価値観の多様化
現代のユーザーは、商品やサービスに求める価値観が多様化しています。商品やサービスが飽和し、競合する今、同じ用途の製品一つであっても、多くの選択肢が存在します。価値や性能だけでなく、ブランドの信頼性や使用感、企業の社会性なども購入決定の要因になっているというのが現状です。そのため、購入や利用の際に一貫してよりよいUXを提供することが、ユーザーに選ばれるためのポイントとなります。
デバイスの多様化
スマートフォンやタブレット、PCなど、多様なデバイスが普及したことで、ユーザーはいつでも手軽にインターネットにアクセスできる環境を手に入れました。それに伴い、ユーザーが商品・サービスに触れる機会も多様化しています。
販売方法も店頭販売に加えてオンライン販売が普及し、購入後のサポートも、訪問から電話やチャットの非対面型サービスが主流になりつつあります。そのため、対面・非対面や使用するデバイスに関わらず、一貫してよいUXを提供できることが重視されるようになりました。
ユーザーエクスペリエンス(UX)と、CXやUIとの違い
UXと似た単語として、「CX(カスタマーエクスペリエンス)」や「UI(ユーザーインターフェース)」があります。どの単語もよく使われるため、混同しないようにするためにはそれぞれの違いを正しく理解することが重要です。
CXとUXの違い
「CX(カスタマーエクスペリエンス/Customer Experience)」とは、顧客が企業とのすべての接点で得る体験を指します。「接点」には商品やサービスの購入・利用時だけでなく、広告、カスタマーサポート、販売チャネルなども含まれます。たとえば、オンラインストアでの購入手続き、広告のデザイン、電話サポートの対応品質、さらにはSNS上でのコミュニケーションなど、顧客が企業と関わるすべてのタイミングでの体験がCXの一部です。
UXとCXは似た言葉のようにとらえられますが、「UX」は特定の商品やサービスの利用に関する体験 であり、「CX」は企業やブランド全体に対する体験を指すため、UXはCXの一部と言えます。
▼「顧客体験(CX)」についてのより詳しい記事はこちら

UIとUXの違い
「UI(ユーザーインターフェース/User Interface)」は、ユーザーと製品・サービスを直接つなぐ接点のことを指します。WEBサイトやアプリの画面上の要素(デザインやボタン配置など)や、パソコンを操作するマウスやキーボードがUIです。
UIとUXの違いを簡単に言えば、UIは「どう見えるか」「どう操作するか」であり、UXはそれを「どう使ってどう感じるか」です。UIがより視覚的にわかりやすく、ストレスなく使える設計となっていれば、総合的なユーザー体験(UX)の満足度は向上するでしょう。UIの設計はUXの重要な要素です。
ユーザーエクスペリエンス(UX)向上のための5つのコツ
UXの向上には具体的なアプローチが必要です。5つの方法を紹介します。
目的を明確にする
商品やサービスを提供する目的を明確にすることで、ユーザーにとって価値のある体験を提供できます。目的をはっきりさせることで、一貫性のあるUXを設計しやすくなります。
ユーザーの調査・分析を行う
ユーザーがどのようなニーズや課題を抱えているのかを知るために、データ収集や調査・分析を行いましょう。社内でペルソナを作成したり、ユーザーにインタビューやアンケートを実施したりすることで、具体的な改善点を見つけやすくなります。
ユーザーは一人ひとりが違った背景を持っていますが、調査結果から把握した共通のニーズや課題をもとにユーザー像を考えることで、それに基づいたUX戦略を構築することが可能です。
▼「ペルソナ」についてのより詳しい記事はこちら
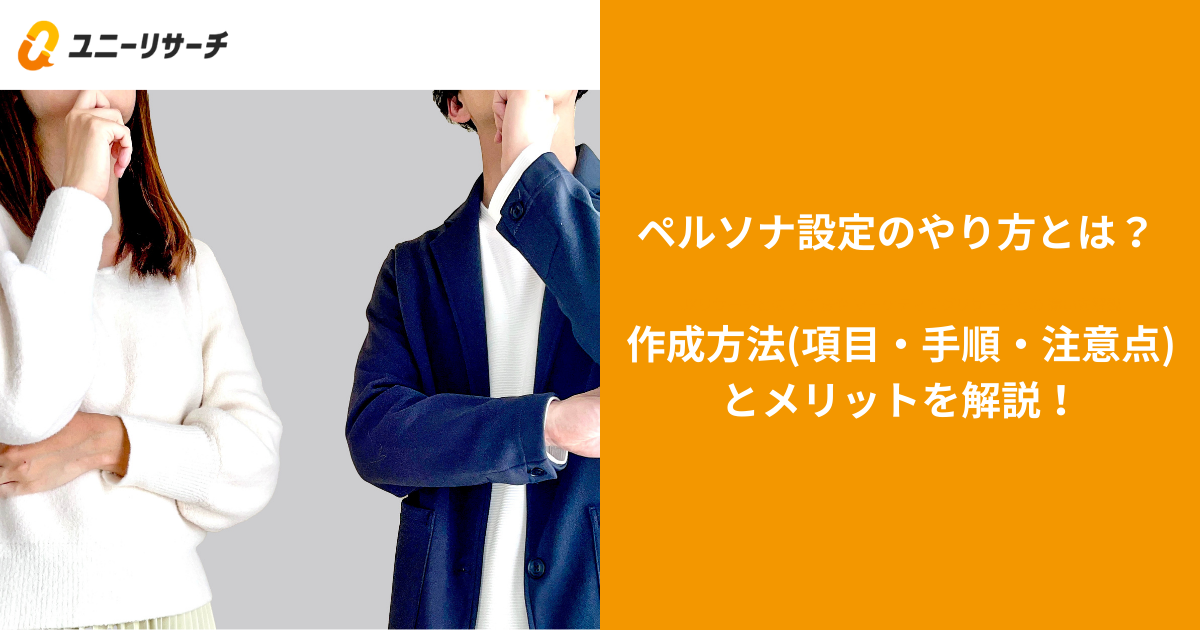
▼「インタビュー調査」についてのより詳しい記事はこちら

▼「アンケート」についてのより詳しい記事はこちら
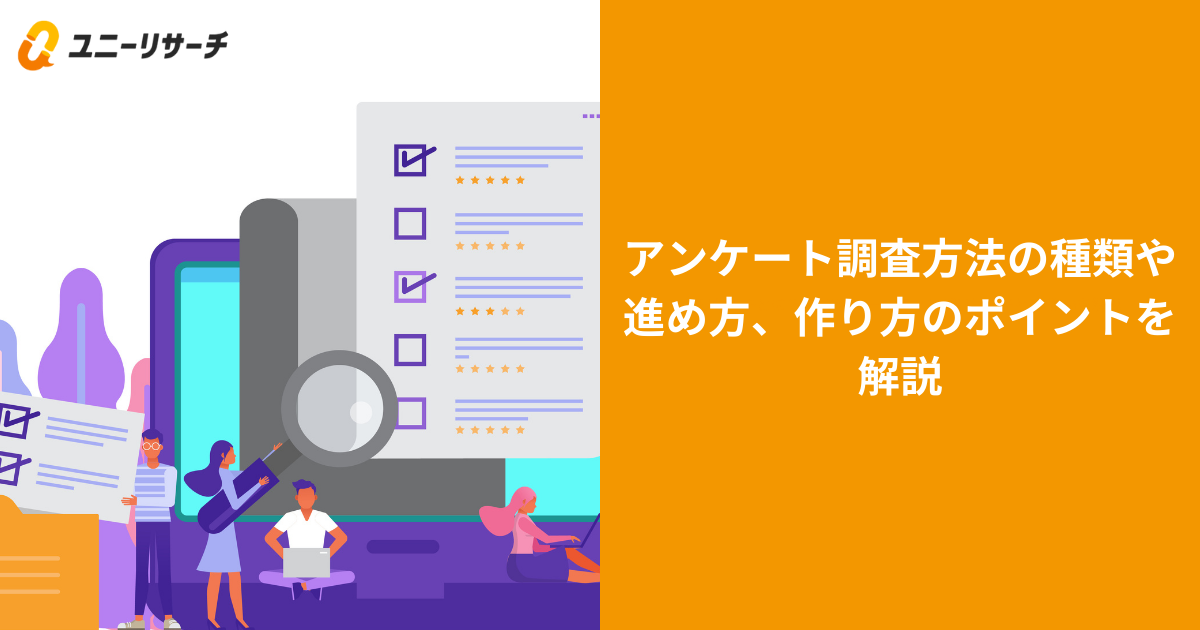
自社の商品が生む体験を意識する
自社の商品やサービスの利用中、及び利用前後にどのような体験をユーザーに提供するかを意識しましょう。ユーザーがどんなニーズで商品を使用し、どのように行動してどんな感情を抱くのかを予想しておくことが重要です。
ユーザーが購入に至るまでのプロセスを旅(Journey)に例え、自社商品・サービスとユーザーの接点(タッチポイント)や行動、感情の変化を時系列で示し、視覚的に見やすくなるようにまとめた「カスタマージャーニーマップ」を作成するのもおすすめです。
▼「カスタマージャーニーマップ」についてのより詳しい記事はこちら

ユーザビリティに配慮した設計をする
使いやすさや直感的な操作性を重視した設計を心がけましょう。なによりも重要なのは、商品やサービスとの触れ合いでユーザーが余計なストレスを感じないことです。購入時のプロセスが煩雑だと、ユーザーは途中で購入を諦めてしまうかもしれません。ユーザーが離脱しないようにするためには、操作ガイドを分かりやすくする、エラーを防ぐ仕組みを取り入れるなどの工夫が考えられます。
また、アクセシビリティ対応や多言語対応など、幅広いユーザーに配慮した設計ができていれば、ストレスを感じるユーザーをより少なくできます。
ユーザー視点で体験する
企業側の視点ではなく、実際のユーザーの立場になって自社の商品やサービスを体験してみましょう。ユーザーがどのように感じ、どんな課題に直面するかを体験することにより、潜在的な課題や改善点を発見できます。また、実際の顧客からのフィードバックを積極的に取得し、改善を繰り返すことで継続的なUX向上が可能になります。
▼「UXリサーチ」についてのより詳しい記事はこちら

ユーザーエクスペリエンス(UX)向上のための調査なら『ユニーリサーチ』
「ユニーリサーチ」は、調査会社を介さずに様々なリサーチを可能にする国内最大級のダイレクトリサーチサービスです。UX向上のためのユーザーからの情報収集に「オンラインインタビュー」や「アンケート」などの調査を「最短当日・従来の調査費用コストの10分の1以下」でご利用いただけます。
ユニーリサーチでは、定量調査専用パネル約2,800万人、定性調査専用パネル数万人の多様なユーザーにアプローチでき、基本属性の選定や事前設問によるスクリーニングで調査の目的に沿わないユーザーとのミスマッチを防止します。
2025年7月時点で3,000社以上が登録、累計リサーチ件数は60,000件を突破しました。ぜひこの機会に、「ユニーリサーチ」をご検討ください。












