
NPS®調査とは?調査方法や質問項目、顧客満足度調査との違いを解説
顧客と企業の関係性を深めるための調査方法のひとつとして、「NPS調査」があります。「NPS®(Net Promoter Score)」は顧客が企業やブランドをどの程度薦めたいか(推奨意向)を測定する指標です。
本記事では、NPS調査の概要や顧客満足度調査との違い、具体的な調査方法やメリットなどを解説します。
NPS調査とは?
企業がユーザーとの関係性を深めるために活用されている「NPS調査」は、「友人や知人にどの程度薦めたいと思いますか?」という問いを基準として、ユーザーが商品・サービスやブランド、企業などをどれほど薦めたいか(推奨意向)を測定する調査です。 「NPS®(Net Promoter Score)」は「Net=差し引き」「Promoter=推奨者」という言葉の通り、周囲に積極的に推奨してくれる「推奨者」の割合から「批判者」の割合を差し引いた値を示します。
ユーザーに対して「あなたはこの〇〇(商品、サービス、ブランドなど)をどの程度友人や知人に薦めたいと思いますか?」という質問をし、その回答を0~10点の11段階で評価してもらいます。
回答は以下の3つに分類されます。
9〜10点:推奨者(Promoters)
7〜8点:中立者(Passives)
0〜6点:批判者(Detractors)
数値が高いほど顧客エンゲージメントも強い可能性が高く、低いと不満が多い状態と判断できます。ただし、NPSは国や業界ごとに基準値が異なり、回答中心化傾向(評価尺度の真ん中よりの回答をする傾向。NPSで言えば5や6など)がある日本では低く出ることも多いです。
▼「顧客エンゲージメント」についてのより詳しい記事はこちら

顧客満足度調査との違い
「顧客満足度調査」とは、製品やサービスを利用した顧客が「どの程度満足しているのか」を測定し、その背景となる要因や改善点を明らかにするための調査手法ですが、実際に推奨やリピートにつながるかどうかは別の問題です。
NPS調査では、「満足しているだけではなく、自分から進んで薦めたいと思う」かどうかがわかるため、長期的な関係構築やリピーター育成に重きを置いた計測手法として活用されています。
顧客満足度とNPSの両方を調査することで、顧客との関係性をより把握し、実際の行動(リピート購入や口コミなど)につながる層を特定しやすくなります。
▼「顧客満足度調査」についてのより詳しい記事はこちら

NPS調査の3つの分類
NPS調査には、大きく分けて「リレーショナル調査」「トランザクション調査」「ベンチマーク調査」の3つがあります。
リレーショナル調査
「リレーショナル調査」は、ユーザーとの長期的な関係性を把握するために行う調査です。一定の期間ごとに実施し、スコアの推移を継続的に見ながら、中長期的なブランド戦略や顧客維持のための施策に活かします。継続調査を行うことで、変動の要因を見極めやすくなるのが特徴です。
トランザクション調査
「トランザクション調査」は、商品購入やサービス利用など、ユーザーとの具体的なやり取りが発生した直後に行う調査です。ピンポイントの体験を通じ、ユーザーがどう感じたかを測定します。リアルタイムでユーザーの声を回収することで、早急な不満解消や改善策実行に繋げられるのが大きなメリットです。
ベンチマーク調査
「ベンチマーク調査」は、競合他社の指標の数値も把握することで、自社が市場全体の中でどのようなポジションにいるのかを客観的に確認する調査です。単に数値の良い・悪いを把握するだけでなく、競合と比べて優れているところ・劣っているところを明らかにできるので、自社の強みや課題を見つけやすくなります。
企業がNPS調査を導入するメリット
企業がNPS調査を導入するメリットを3つご紹介します。
顧客ロイヤリティの高い層がわかる
NPS調査で「推奨者」「中立者」「批判者」の3つのユーザー層の割合を把握することで「顧客ロイヤリティの高い層」を特定でき、その属性のユーザーに対するアプローチを強化する検討材料として用いることができます。
「顧客ロイヤリティ」とは、ユーザーが特定の企業に抱く愛着や信頼のことです。忠誠心を表す「Loyalty」が言葉の元となっており、ユーザーの「感情」に焦点を当てた概念です。
競合他社との比較がしやすい
ベンチマーク調査を行えば、自社のNPSが高いか低いかだけでなく、市場全体から見たときの自社の立ち位置を把握することができ、その結果に応じた施策を考えることができます。
サービスや商品開発に活かせる
NPS調査では、NPSスコアを出すための定量調査の質問だけでなく、自由回答の定性調査の質問も一緒に尋ねることができます。推奨意向度の背景にある「なぜ推奨したいと思うのか」「推奨したくない理由は何か」といったユーザーの生の声を収集することで、新たな商品開発や、サービスの改良につながるヒントが得られるでしょう。0〜6点をつけた批判者からの声も、改善の余地を教えてくれる貴重な情報源になります。
▼「定量調査」「定性調査」についてのより詳しい記事はこちら

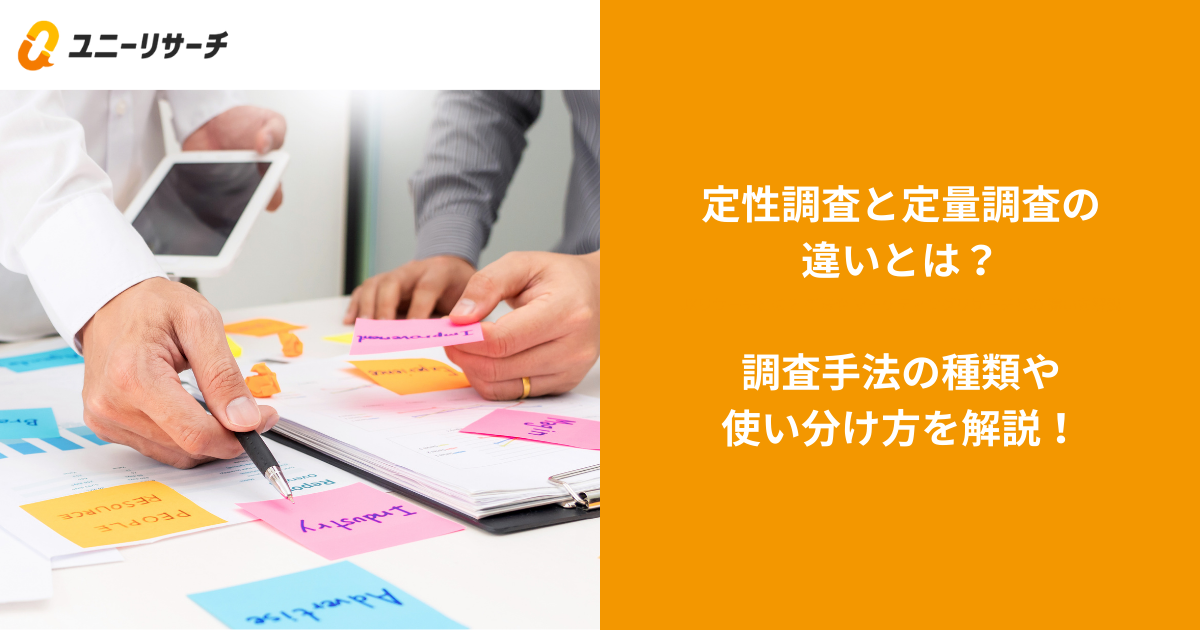
NPS調査を進める流れ
NPS調査の一連の流れを紹介します。
調査の目標設定をする
最初に、「自社のブランドロイヤリティを定期的に把握し、それを踏まえてロイヤリティの高い層の維持・育成策を強化したい」、「新規購入者の購買体験に対するフィードバックを集め、接客対応を改善したい」、「競合他社とのポジションを確認し、自社の差別化戦略を見直したい」など、NPS調査を行う目的を明確に設定します。
目的がはっきりしないまま実施してしまうと、どのタイミングでどんなユーザー層を対象にすればいいのかが曖昧になり、結果的に活用しづらいデータになってしまう恐れがあります。
調査の対象と方法を決める
次に、上記の目的を踏まえて、どんなユーザーにどんな方法でNPS調査を実施するかを決めます。
例えば、
リレーショナル調査:一定期間ごとに既存ユーザーに調査依頼を送付
トランザクション調査:購入や問い合わせの後に調査依頼を送付
ベンチマーク調査:大規模なユーザーパネルを持つ調査会社やセルフリサーチサービスを利用して、自社顧客だけでなく競合製品利用者にも調査を依頼
というように、ユーザーとの接点を考慮しながら、最適な調査方法を選びましょう。
アンケートの質問項目を作る
NPS調査では、「この商品やサービスを友人や知人にどの程度薦めたいと思いますか?」という基本の質問に加え、補足となる質問や自由記述欄を設けるのが一般的です。
「なぜその点数をつけたのか?」「改善してほしい点はどこか?」などの定性情報を集める設問も入れることで、より充実した分析結果が得られます。
▼「アンケート」についてのより詳しい記事はこちら
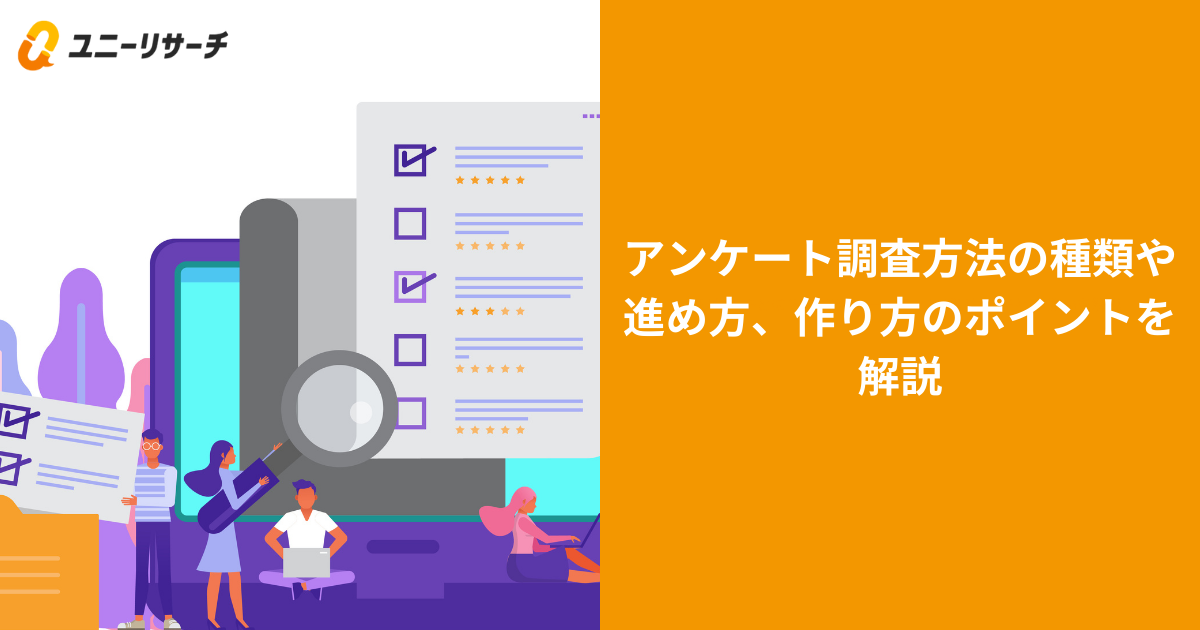
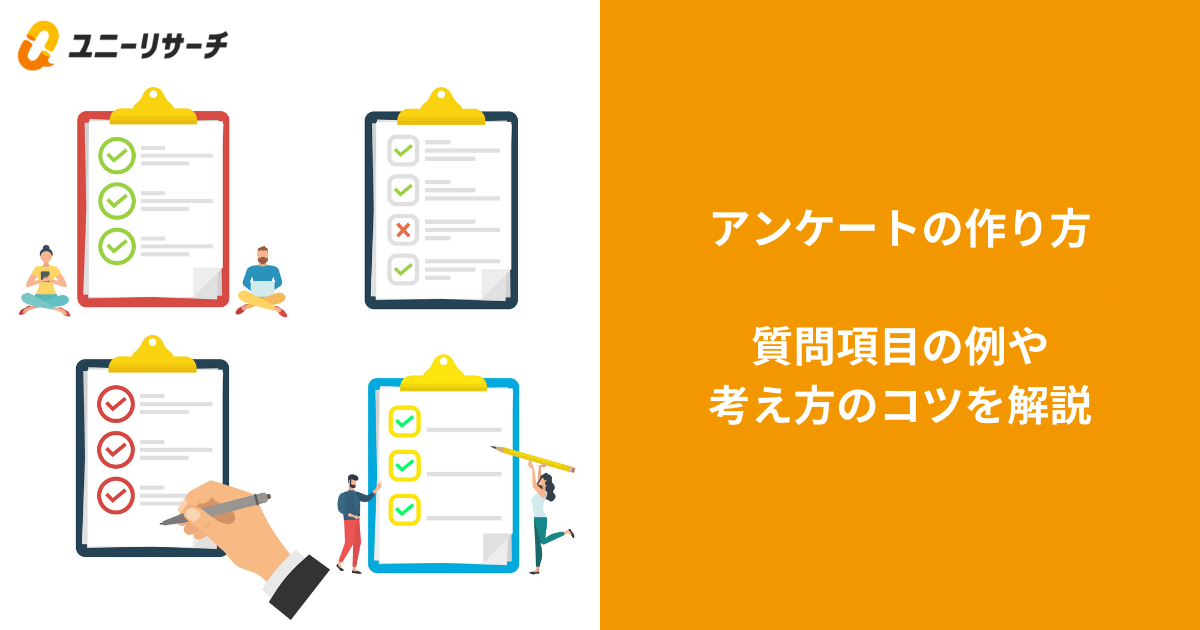

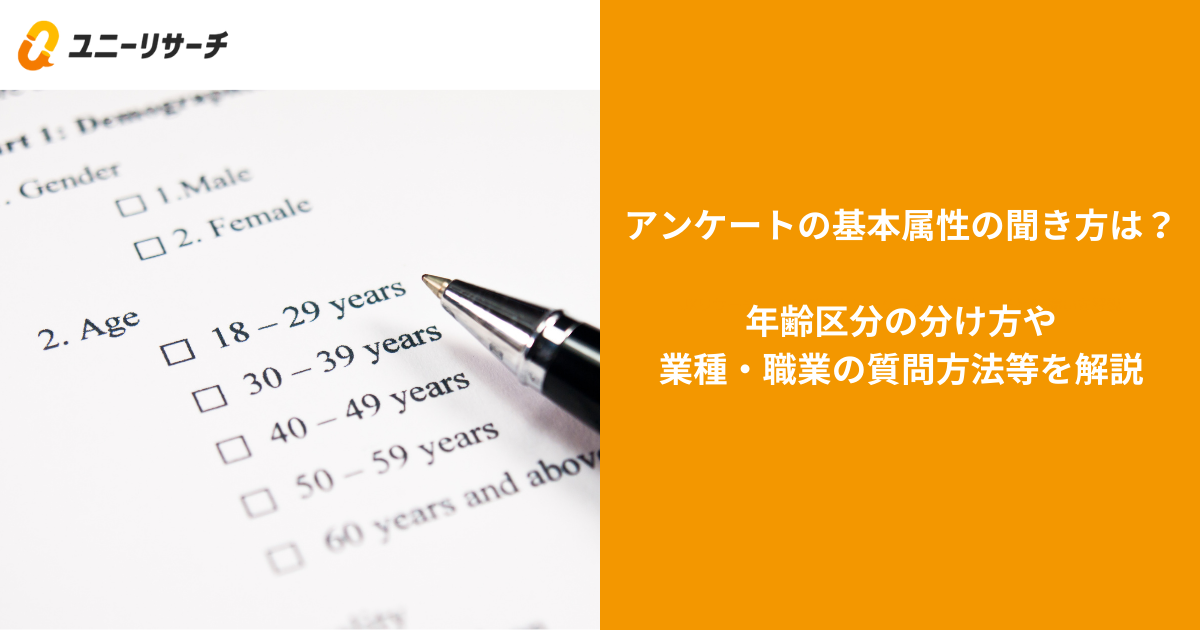
調査を実施する
調査設計が整ったら、調査を実施します。回収したデータは集計し、推奨者・中立者・批判者の割合やコメント内容を整理して分析します。
分析結果は社内で共有し、必要な施策を検討します。調査結果の分析だけで終わらず、改善に繋げてこそNPS調査の効果が発揮されます。
NPS調査を実施する際のポイント
NPS調査を行う際に以下のポイントを押さえることで、より有益な分析結果を得ることができます。
競合他社のスコアと比較する
ベンチマーク調査で、競合他社のNPSスコアを把握し、自社と比較してみましょう。自社の数値が高いように見えても、同業他社の平均より低ければ、改善策を練る必要があります。逆に平均を上回っていれば、強みをさらに伸ばす方法を検討できます。
定性的な方法も組み合わせる
定量的なNPSだけでなく、定性的な調査も組み合わせて「なぜその数値になったのか?」という背景を深堀りしましょう。読み解くためには自由回答やインタビューなどの定性調査が不可欠です。
アンケートに自由回答の設問を入れたり、合わせてインタビューなどを実施したりすることで、ユーザーが実際に感じている期待や不満を把握し、より具体的な施策に落とし込みやすくなります。
▼「インタビュー」についてのより詳しい記事はこちら




日本ではスコアが低くなりやすい点に留意する
日本では満点や高いスコアをつけることに抵抗を覚える人が多いです。そのため、海外の企業とNPSと単純に比較してしまうと、日本企業のNPSが相対的に低く出やすい傾向があると言われています。必ずしもNPSの絶対値や他社との相対比較だけでなく、自社の過去のスコアからの推移にも注目して分析するのがおすすめです。
精度の高い質問を設計する
NPS調査は「友人や知人にどの程度薦めたいと思うか?」という質問が中心になりますが、それ以外にも精度の高い質問をしっかり設計することで、「具体的に何が良かったか」「どこを改善してほしいか」などのユーザーの声を得ることができます。このような情報が実際の改善施策を考える上での大きなヒントとなるため、質問の設計は重要です。
NPS調査に国内最大級のダイレクトリサーチサービス『ユニーリサーチ』
「ユニーリサーチ」は、調査会社を介さずに「最短当日・従来調査費用の10分の1以下」での様々なリサーチを可能にする国内最大級のダイレクトリサーチサービスです。数万人の多様なユーザーにアプローチでき、基本属性の選定や事前設問によるスクリーニングで調査の目的に沿わないユーザーとのミスマッチを防止します。
「アンケート」や「オンラインインタビュー」などのリサーチサービスを利用したNPS調査にもご活用いただけます。2025年7月時点で、登録企業3,000社、累計リサーチ件数60,000件を突破した「ユニーリサーチ」をぜひこの機会にご検討ください。












